健康ブログ注意点の総まとめに入ります。
実際にSNSや個人ブログサイトで主に健康食品(サプリメントなど)レビューなどを投稿する際に、使用してOKとNGの判定は??
※今回、めっっっちゃ長いです。置き換え言葉の例をたくさん載せていますので長々としていますが、閲覧者様のヒントになれば幸いです。
ただ、あくまで参考にして、ご自身で調べてくださいね。
当方、専門家ではありませんので間違いもあるかもしれませんし、保障はしかねますので。
さて、レビュー等を書く際には主に4つの事項に注意が必要です。
製造・販売する側と、レビューを書いたりする消費者側とで少し違ってくるので併せて説明していきます。
その後、基本的なNG言葉とOK言葉、置き換え言葉まとめをしていきます。
目次からスキップしてくださいませ。
4大禁止事項(大前提)
①.成分本質(原材料)
専ら(もっぱら)医薬品で使われる成分を含有しているものは医薬品と判断されます。また、医薬品で使われない成分で構成される製品であっても、医薬品的効果効能を謳うと医薬品と見なされます。
『健康食品は医薬品ではないので薬効成分が含まれているものはダメ』
『医薬品でもないのにまるで医薬品クラスの効果があると謳うのもダメ』
これは消費者側にはあまり関係ありませんが、たまに医薬品クラスの効果を謳っているサプリメントがありますので、きちんと表示されている文章を読んで、信頼あるかどうか判断するよう心掛ける必要がありますね。
②.効果効能の標ぼう
商品のパッケージや包装含め、販促物、広告で次のような効果効能を標ぼうするものは医薬品と見なされます。
①疾病の治療や予防に関する効能効果(例:糖尿病、高血圧、ガン、便秘の改善など)。
②身体機能の増強を目的とする効能効果(例:疲労回復、体力増強、老化防止、精力増強など)。
③医薬品的な効能効果を暗示する表現(例:特定の名称やキャッチフレーズ、成分、製法、由来などから暗示される効果)。
①については、健康食品は医薬品ではないので病気の予防・診断・治療を目的としていないため、いかなる場合でも絶対にNGです。
②については難しいですよね。一見、「それはイイのでは?」と思いがちですが、食品は食品なのです。特化しすぎてる効果に保障はありません。ですからNGです。
また、身体の部位を特定して効果があると謳うのもNG。
③成分本質と同様ですね。医薬品クラスであることを暗示する(匂わせる)ことはNGです。
例として、「必ず〇〇が改善する」、「確実に効果がある」、「わずか数日で効果が実感できる」、「すべての人に効果あり」など、不確実な、または絶対的な表現は消費者の方へ過剰な期待を持たせる表現は原則禁止されています。
他にも、
【最上級表現】
「日本一の効果」、「最高の効き目」、「〇〇の王様」など。
効能効果等又は安全性についての最大級の表現は消費者に過度な期待を抱かせるため禁止されています。
【権威ある第三者が勧めている旨の表現】
「医師もおすすめ」、「産婦人科医推奨」、「〇〇成分は学者も推奨」など、
人の認識に影響が大きい医者や団体などが推奨しているという表現は原則NGです。
※こちらは別途詳しく記事にします。
【他社の製品の誹謗、比較広告】
「〇〇社よりも〇〇成分配合」、「〇〇社より優れた商品」など
他社商品と比較して自社の商品が優れていると謳う広告は原則禁止されています。具体的な商品、ブランド等を明らかにしなくても、不適切な表現として指摘が入る可能性があります。
こうした最大級表現や権威ある第三者オススメ、他社との比較。これらは製造・販売する側だけでなくレビューを書きたい消費者側も、ついつい付け足しがちです。ご注意を。
また、
『安心・安全』などの表現も「子どもでも安心」、「国内生産なので安心(安全)」、「安全性は確認済み」、「無害」など、『安心』は個人の主観であり、また『安全』文言についてもそれが確実である保証をするような表現は禁止されています。
難しい!
実際にクリニックなどで先生に勧められた商材などは、医薬品や医薬品部外品であることが多いので、健康食品の場合はそうはないと思います。
【医薬部外品】の場合は、承認されている効果・効能ほ範囲でのみ表現することが許されていますが、その他の最大級表現や他社との比較、治った、安心安全、などは健康食品と同様に原則禁止されています。
よくよく注意しましょう。
安心安全も、自分が使って大丈夫だったから、は根拠になりませんし、安全性確認済みも、100%安全ですってわけではありません。100%でないものに、そうであるかのように誤認識させてしまうような表現は厳禁、ということですね。
③.商品の形状
錠剤、丸剤、カプセル剤、アンプル剤などは、一般的に医薬品として認識されているため、これらの形状を持つ製品は医薬品と見なされることが多くなります。
※すべてではない。
健康食品の場合、食品であることが明示されていれば、形状だけで医薬品かどうかは判断されませんが、消費者様を騙す意図があると判断される場合はその限りではないため、サプリメントなどを扱う事業者様は特にこの点に注意です。
『医薬品と誤解されるような形状はダメ』
『健康食品であれば食品であるとわかるように明記していればOK』
消費者側は製造していないのであまり関係ないように思うかもしれませんが、注意すべき点は、ちゃんと表示を見て医薬品なのか健康食品なのかしっかり判断・理解することですね。
④.用法用量
服用方法(服用量、時期、間隔等)を詳しく定めてるものは医薬品と判断されます。ただし、健康食品であっても過剰摂取や連用による健康被害が心配される場合は、摂取の目安を示すことが必要なケースもあるため、「1日◯錠目安」などの書き方であれば問題ないと判断されます。
これも、「別に問題なくない?」と思いがちですが、医薬品は明確に定めます。処方通りに服用してもらわないといけませんからね。
健康食品の場合は、明確に定めると医薬品と判断されちゃうのでダメ。
ただし、過剰摂取による健康被害の恐れがあるので『目安』という形で表記します。
消費者側は、目安量をきちんと守って摂取しましょう。
感想を書くとき絶対に避けるべきNGワード4つ
⚠️まずココが大事💡
たとえ、機能性表示食品であったり特定保健用食品であったり、商材パッケージに『届け出内容に沿った機能』が表記されていたからといって、消費者側のレビューは効能を評価する立場にはないため、効果を語るのはNGです。
例: 機能性表示食品【免疫ケア】と表記されている
→「免疫力が上がった」、「風邪を引きにくくなった」、などは疾病予防・治療と解釈されるため絶対的NGです。
つまり、感想・レビューを書くときに薬機法上でNGとなる用語は、化粧品・医薬部外品など、それぞれのカテゴリーに定められた標ぼう可能な効能効果の範囲を超えた表現が該当します。
『ここまでなら表現してもいいけど、それ以上の表現は医薬品表現であったり食品であれば過剰摂取とかによる健康被害を招いてしまう恐れがあるからダメですよ~』
ってことですね。
特に以下の4ワードは使用自体がNGになります。
『安心・安全』→例:これで老後も安心
『治る』→例:あせもが治る
『改善』→例:ニキビが改善
『効果』→例:ダイエットに効果的
①.安心・安全の保証
「〇〇の商品の安全性は証明されています」、「〇〇を使用すれば老後は安心です」など、医学薬学上で認められた範囲から逸脱した表現には注意が必要です。また、製品の機能などについて、消費者に誤解を招く表現は薬機法で厳しく取り締まられるため、併せて注意しましょう。
『効果が確認されている』=『効果が必ずある(保障)』は、全くの別です。
個人差も含めてその効果や安全性に保障のしようがないものを、保障があるかのように謳うことはNGです。
言葉遊びのようですが、ココの言葉の認識に注意。
消費者側は、このようなNG表現をしている商品は信頼性に欠けるので手を出さないよう注意することと、どんなものも『安全性に保障はない』ということを理解しましょう。
100%安全なものなどありませんし、たとえば医薬品でもないのに10年20年先の老後なんてエスパーじゃあるまいしわかりゃしませんから、そうしたことを保障できるはずもないのです。
②.治る・治癒する等の表現
「〇〇が治る」といった表現の使用は絶対にNGです。たとえば、「あせもが治る」「特定の病気が治る」などの表現をした場合、行政指導や禁固刑を受けるケースもあります。実際、過去には認められた範囲から逸脱した表現をしてしまい、行政指導を受けた商品も存在します。
消費者側が注意すべき点は、まさにここの理解です。健康食品等は医薬品ではないので、病気の予防・診断・改善・治療を目的としていないこと、そのため『治る』といった表現は用いてはいけないものだということ。
すべての健康食品共通のことなのでしっかり理解しましょう。
『治る・治す』はお薬オンリー。これが絶対です。
『改善』もまったく同様に、改善を目的としているのは医薬品のみなのでNGです。
③.効果・効果的等の表現
特定の病気や症状に「効果的」といった表現にも注意が必要です。たとえば、「ダイエットに効果的」、「便秘予防に効果的」などの表現が挙げられます。
「効果的くらいならイイんじゃない?」
と思いがちですが、ダメなんです。
同じ商品を使ったとしても、人それぞれ効果効能が異なります。年齢・性別)生活習慣、様々。
したがって、人によって効果効能が異なるのであれば、上記のような表現は消費者に誤解を招く可能性があるため、使用は避けるべきということです。
「でも、個人差あっても効果ゼロじゃないならイイんじゃない?」
とも思いがちですが、そもそも『効果がある』と断定すること自体がダメなんです。
効果をまったく得られない方もいますから。
ココもお薬との違いですね。
NGワードを避けて表現する【置き換え言葉】の考え方
さてさて、じゃあどうしよう、困ったぞ。どうやったって伝えたいレビューを伝えられない。
なので、【置き換え言葉】でその問題をクリアします。
置き換え言葉、まさに言葉遊びですね。でも法律によって明確に禁止用語が定められているのであれば、逆にいえばその禁止用語さえ避ければおおむね問題にはならないということです。
まず考え方として例に挙げてみます。
薬機法(旧薬事法)で「効果」と表現するのが難しい場合は、「機能性」、「改善(法律で認められている商品に限る)」、「サポート」、「促進」などの表現に言い換えることで、表現の幅を広げることができます。
具体的な例:
「効果」→「機能性」として考えてみる→「肌にうるおいを与える機能性」
「効果的」→「サポート」支援してくれると考えてみる→「肌の乾燥をサポート」
「効果」→「改善(認められている商品に限る)」→「乾燥による小じわを目立たなくする」
「効果」→「促進」最終的な評価としての効果ではなく、なにをしてくれる成分なのかと考えてみる→「細胞の活性化を促進」
このように、『結果』という最終評価で言葉を選ばずに、『そもそもどんな働き?』という、メカニズム的なところを考えてみると置き換え言葉は見つけやすいかと思います。
では、禁止用語を避けつつどんな表現をしていったら望ましいか、掘り下げていきましょう。
代表的なNGワード、【改善】という言葉の意味から見つめ直す
「〇〇を改善」は例外を除いて基本的にNGワードの1つです。
※例外:厚生労働省から認可を受けた「シワを改善する」有効成分が含まれている医薬部外品においては、承認の範囲内での表現は可能です。このような例外を除いてお話します。
たとえ本当に、実際に、本人の手応えとしてその商品を使用した結果に効果が得られたとしても、『改善した』とは言ってはいけません。
※『効果』の標ぼう
繰り返しますが医薬品ではありませんから予防・診断・改善・治療を目的としていないためNGであること。
そして、本人に効果があった(と感じた)背景に、もしかしたら食生活も変わったかも?よく寝るようにしたからかも?遊びにいってストレス発散したからかも?季節性の不調だったかも?
様々な要因がありますので、その商品だけで症状を改善できるのか否かは人それぞれ異なりますし、断定ができません。それこそその判断ができるのは医師(つまり診断)だけです。
そのためNGなのですね。
そしてNGだからこそ、加えて誤解を招く表現(医薬品クラスの効果)や『オススメ!!(誘引)』だったり、『めっちゃ良かった!!(誇大広告)』の1つとして規制されてしまう可能性も高いです。
「神経質すぎる……」と思っちゃいますよね。でも、SNSの情報を漫然と信じてしまうユーザーが多い世の中ですから、健康を守るためには必要な法律なのです。
『改善』の言い換え言葉の例
「~に役立つ」:
改善の代わりに、客観的な効果を伝える表現として利用できます。「ニキビケアに役立つ」など。
「~をケアする」:
ニキビ跡ケア、肌の乾燥ケアなど、症状をケアするという表現も可能です。
「~を防ぐ」:
予防を目的とした表現として、化粧品などで「ニキビを防ぐ」など、使用できます。
「~をサポートする」:
症状の改善をサポートする、といった表現も可能です。
「~を整える」:
体調や肌の状態を整えることを表現する際に使用できます。
※ただし使い方に注意が必要(後述)
ふむふむ、と思ったかもしれませんね。
原点回帰してみましょう。
サプリメントとは『補う』もの。食品。
であるからして、『治す』はNG。治せるのは医薬品だけ。
①ケア【care】
1.注意。用心。
2.心づかい。配慮。「アフター—」
3.世話すること。また、介護や看護。「患者を—する」「—ワーカー」
と辞書にあります。
意味合いから考えて、補うモノ『サプリメント』の範疇はケア(配慮・世話)と言えますね。
②サポート【support】
1,「支える」
2.「援助する」
3.「支持する」
と辞書にあります。
サプリメントの範疇にピッタリですよね。
③整える
「乱れのないようにする」
「望ましい状態に調整する」
と辞書にあります。
これはちょっと解釈が難しいですよね。『改善』と捉えられないこともない。
ただ、薬機法のいうところの改善とは医薬品として判断されるもののみという角度から、『そこまで高い水準の効果はない』というのがサプリメントの前提となりますので、整えるもほぼ『サポート』と同義として用いると考えると良いかもです。
文章作りに悩んだとき、『サポート』よりイメージが『整える』のほうが近かったら『整える』と表現してみる、とか。
※『直接的に整える働き』と捉えられる表現はNGで、『間接的に整える』という表現はOKとなります。
同様に、『促進』も改善と似て非なる表現なのでOK。
『機能性』の有無は、機能があることが明記されている機能性食品や特定保健用食品などの場合は用いることができます。
機能はある、けど必ずしもその機能が100%表れて健康状態が改善するわけではない→医薬品ではないから。
つまり『機能があること自体』までは言ってもOKなわけですね。
それ以上の表現をすると誇張として判断される恐れがあるので注意。
こうして並べてみますと、【改善】と置換できる表現には、
「ケアする」、「サポートする」、「整える」、「促進する」、「機能性」
と5つは挙がります。
選択肢がこれだけあれば、まぁまぁなんとか法に抵触しないで文章表現できそうですよねーーーって、ところがどっこい、まだ注意すべき点があります。
代表的なNG表現、直接的・特定的な表現もNG
NGワード以外にも気をつけなければならない表現があります。
薬機法でNGとされる表現例には先に挙げたように直接的な効能効果を訴求する表現として安心・安全・治る・改善・効果、とみていきましたね。例文としては、
「二の腕が細くなる/なった」
「便秘に効果がある/あった」
「腸内環境を整える/あった」
など、です。
こうした文章の中には、NGワード以外にもNGな表現が含まれています。
それは、【特定の部位】です。
お腹や肌など、身体の一部を特筆し、その部分への効果を暗示する表現も禁止されています。
この身体の一部とは、身体を構成している『筋肉』であったり、『免疫力』なども該当します。ココに注意⚠️
よく見聞きしますよね、「筋力アップ」ですとか、「免疫力向上」って。
こうした身体機能の増進・増強を訴求する表現はNG。
また、例に挙げた通り「便秘に効果がある」といった疾病予防や治療を暗示する表現も、勿論のこと医薬品ではないのでNGです。
もう耳にタコ(文だから目にタコかな)ですよね。
「じゃあなんならいいの?」
薬機法で許容される表現方法をとにかく模索していきましょう。
たとえば、抽象的な表現ですね。置き換え言葉のことを踏まえて例にしてみますと、
「日常的な腸内の健康維持に役立つ」、「内側から体内環境を整える」など。
あるいは『気分的な効果』を訴求する表現として、お腹のことなら
「朝からすっきり」、など。
健康増進を訴求する表現は『筋肉』という言葉を用いず、
「元気のために」など。
専門家さんによるQ&Aを一部紹介
専門家さんがお答えしている具体的な例てして、
①キューピーさんの【よ・い・と・き】
この商品には酢酸菌酵素が含まれていますが、「酢酸菌酵素がアルコールを分解する」という訴求はOK?
答えはOK。
なぜなら、体の具体的変化を述べると薬事法違反になりますが、
「酢酸菌酵素がアルコールを分解する」という訴求は体に関する話ではなく、ヴィトロ(試験管)レベルの話だからです。
もう1つ専門家さんがお答えしている例をみてみましょう。
②便秘系のサプリで「体内環境を整える」というワードを使いたいのですが、NGでしょうか?抽象的なので問題ないように思うのですが。
答えはNG
健康食品は「体内」の変化を謳えません。したがって「体内環境を整える」のように体内に作用する旨の表現はNGです。
ただし、「内側から身体環境」に作用する旨の表現は、体内の変化ではなく、食品を内側に取り込んでそれが内側から身体に作用するという意味なのでOKでしょう。例えば「内側から身体環境を整える」や「中から身体をきれいにする」等の表現は問題ないと思います。
※薬事法ドットコムさんより抜粋
だそうです!これ個人的にすごく勉強になりました!
とにかく上手いですよね。モヤっとする表現でも、ちゃんと説明を聞いてみると「なるほど!」ってなる。
ということで、だいたいこんな感じになります。
うーむ、ふわっとしてて若干納得いかない感は残りますよね。
伝えたいことが好きに伝えられないジレンマ。
でも、こればっかりは法律だから仕方ない……。
そしてとにかく難しい……。
頑張って言葉遊びの練習をしましょう。
次回で最後。二回に分けてカテゴリーごとに使い回しできる具体例を一覧にしながら挙げていきます。
関連記事はコチラ↓
第3章 【薬機法(第66条)】についてもっと詳しく各項目を具体的にみていこう
カテゴリー『個人ブログサイトで健康食品のレビュー等を行う際に知っておくべき法律と注意すべき表現のまとめ』はコチラ↓
個人ブログサイトで健康食品のレビュー等を行う際に知っておくべき法律と注意すべき表現のまとめ

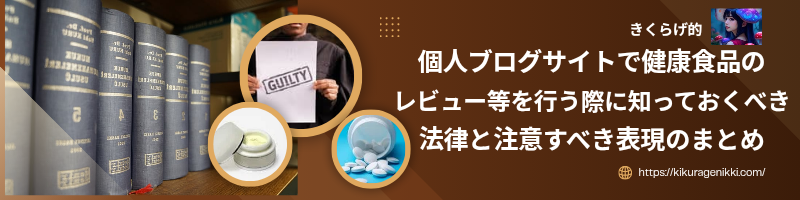
コメント