ではそれぞれ種類を解説していきます。
今回は経腸栄養剤の王様ともいえる①エレンタールについて、その仕組みと成分、用法について解説します。
①『成分栄養剤(完全消化態栄養剤)』
エレンタールはアミノ酸・糖質・脂肪・電解質・微量元素・ビタミンを成分とするパーフェクトな経腸成分栄養剤です。
前述の通り消化をほとんど必要としない成分で構成された最も吸収されやすい高カロリー栄養剤で、腸の安静をはかりながらバランスのよい栄養を摂ることができます。
食事を摂ることが困難な重度の活動期場合や、手術前後の栄養管理に使用します。
寛解期でも維持と補給目的として使うこともあります。
消化の必要なたんぱく質は含まれておらず、吸収されやすいアミノ酸がバランスよく配合されています(たんぱく質を分解済み→アミノ酸の状態にしている、と捉えるとわかりやすいかと思います)。
また、脂肪の配合も最小限となっており、腸を安静に保つことができます。
栄養分はそのまま腸から吸収され、便もほとんど出ません。
粉末となっており、ぬるま湯で溶かした経口あるいは経管で服用します。
※経管とは、鼻から細いチューブを胃まで挿入して点滴のように滴下する方法です。俗に『鼻チュー(びちゅー』と呼ばれています。
エレンタールはアミノ酸の苦味えぐみがかなり強く、そのままではかなり服用困難な味です。専用のフレーバーが10種類以上ありますので、飲みやすいフレーバーをつけたり、変化をつけたりもできます。
とろみをつけてムース常にしたり、ゼラチンでゼリーにして食べることも可能ですので、個人個人で好みにカスタムできます。
必要に応じて医師や栄養士と相談しましょう。
※私個人は、お腹が痛くなってしまうのであまり合いませんでした。あと味はフレーバーをどうしようとゼリーにしようとなにしようと、かなりきついです。
エレンタールの導入
・導入と服用量は、経管の場合、エレンタール配合内用剤80gを300mLとなるような割合で水またはぬるま湯に溶かし(1kcal/mL)を鼻から管を入れる鼻腔ゾンデ、胃瘻、または腸瘻から、十二指腸あるいは空腸内に1日24時間持続的に注入します(注入速度は75~100mL/時間)。
経口摂取の場合、年齢や体重、症状などによって適宜増減しますが、標準量として成人1日480~640g(1,800~2,400kcal)を投与します。
導入時は、初期量は1日量の約1/8(60~80g)を所定濃度の約1/2(0.5kcal/mL)で投与開始し、状態により、徐々に濃度および投与量を増加し、4~10日後に標準量に達するようにします。
「粉でどれくらい?溶かしてどれくらい?」がなかなかわかりにくいかもですが、基本的に『gグラム』で言われたら粉のほうと捉えてください。
医師は基本的にグラムでどれくらい摂ると話しますので。
エレンタール溶解液の作り方
・溶かした液剤の作り方は、エレンタール配合内用剤1袋80gを1kcal/mLに調製する場合は、容器に水またはぬるま湯を約250mL入れ、エレンタール配合内用剤1袋を加えて速やかに攪拌します。この場合、溶解後の液量は約300mL(1kcal/mL)となります。
エレンタール配合内用剤プラスチック容器入り1本80gを1kcal/mLに調製する場合は、水またはぬるま湯で溶解し、液量を約300mLの目盛り(凸部)に調製します。
経口の場合も経管の場合も少量で開始し、徐々に増量するのが一般的です。
寛解期でしたら濃度を上げて1度に飲む量を減らすことも可能です。
経過観察と医師との相談次第ですね。
エレンタールの欠点
パーフェクトと言いましたが、完璧なようでいて欠点も勿論あります。
人によりますが脂肪肝になりやすい人もいます。
そしてどの経腸栄養剤も同じですが浸透圧が高いので、ぐびぐび早く飲むとお腹がゴロゴロしますので、15~30分かけてゆっくり飲む、あるいは滴下する必要があります。
※浸透圧が高い→すごーく濃い→薄くしないと吸収できない→体液(腸液)ざたくさん出る→お腹ゴロゴロ、です。
ゆっくりでしたら全然問題ありません。
その他には腹痛やお腹の張りや吐き気が起こることもあります。
エレンタールだけでは脂肪が不足するため、定期的に『脂肪乳化剤(イントラリポス)』が必要となります。
単純に脂肪を補うだけでなく、イントラリポスを点滴することで効率良く必須脂肪酸を補給することができ、脂肪肝を予防することができます。また炭酸ガスの蓄積を防ぐ、などがあります。
注意事項として、イントラリポスは精製大豆油を主成分とする脂肪乳剤であり、電解質やアミノ酸との混合により経時的に粒子の粗大化や凝集をきたし、肺塞栓が発生する可能性があるため、基本的には他剤とは混合せず、末梢静脈からの投与となります。
また、脂肪乳化剤は投与してから脂肪を十分に代謝する必要があるため、時間をかけてゆっくり投与します。
また、エレンタールのみの場合が長期間続きますと、腸の絨毛(じゅうもう:小腸の内面の粘膜に密生している指状の小突起。高さ0.2〜1mm)が次第に小さくなり、内面の粘膜のヒダヒダがなくなりツルツルになってしまいます。そうなりますと、普通の食事が消化吸収できなくなってしまいます。
ですが、ツルツルになっちゃうのは相当な期間の場合ですし、医師もこれを避けるためになるべく制限食を摂れるように治療を運びますし、それほど心配はいりませんが、一応医師から説明はあると思います。
これが、前回お話した制限食少しでも食べてお腹を使わなければいけない理由ですね。
乳幼児用のエレンタール
『エレンタールP(新生児・乳幼児用成分栄養剤)』
乳幼児の発症はまれですが、発症した場合は重症になりやすい傾向があります。症状が出ていると十分な栄養が摂れず、成長にも深刻な影響が出るため、消化管に負担をかけずに十分な栄養を摂る目的で、2歳未満の乳幼児には『エレンタールP(乳幼児用配合内用剤)』が処方されることがあります。また、2歳以上であっても、医師が治療上必要と認めた場合は処方されることがあります。
ノーマルなエレンタールと同様に消化をほとんど必要としない成分で構成された、吸収されやすい高カロリー栄養剤で、腸の安静をはかりながら栄養を摂ることができます。消化管の病気があり、食事や未消化態タンパクを含むミルクなどで栄養を摂ることができない新生児・乳幼児に用いられ、手術前後の栄養管理にも使用します。
脂肪は新生児・乳児に必要なため、エレンタールPには、ノーマルなエレンタールより多く配合されています。また、アミノ酸も、母乳を参考にバランスよく配合されています。
0歳児でクローン病が確認され治療が行われているニュースを初めて記事で読んだときは驚きました。
産まれてすぐ発症することにも驚きですが、どうやってクローン病って確定できたんでしょうね?
少し前向きまでは大人でも確定に至るまで難しかったのに、日進月歩、医療の発展は凄まじいものですね。
※お薬情報参考元:IBDプラス/クローン病の治療で使用する主なお薬一覧
次回は②の半消化態栄養剤をまとめて紹介、『栄養療法-⑤経腸栄養剤-②その他の経腸栄養剤』に続きます。
カテゴリー『内科治療』はコチラ↓
サクッとクローン病治療の概要をまとめて知りたい方はコチラ↓

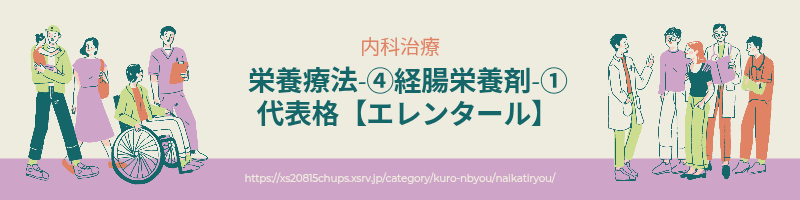

コメント