まずはどんな法律によって規制されているか知る必要がありますよね。
投稿をする際に一番配慮しなければならないのは【薬機法】(旧:薬事法)になるかと思いますが、これ以外に【景品表示法】、【健康増進法】、【医療法】、があり、この4つの法律が健康ブログを運営する上でしっかりと理解・対策をしていかなければならない法律になります。
1つずつざっくりみていきましょう
①薬機法
これは旧薬事法ですね。
その中で以下の法律に抵触しないように細心の注意を払わなければなりません。
「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」
※薬機法第66条
『広告』、とありますね。個人ブログサイトも厳密には『広告』に該当するそうです。
また、『何人(なんぴと)も』とありますね。広告収入などで収益化していない非営利ブログサイトであっても、この法律を犯してはならないということです。SNSやブログ、パンフレットとかどんな媒体だろうとダメなもんはダメ。
法律で認められていない表現を用いると違反になります。
「なにをしたらダメなの?」
医薬品に関しましては虚偽は勿論のこと、誇大な効果などを謳ってはいけません。また、特定の医療機関などを誘引したりするのもNGです。
化粧品や健康食品に関しましては、医薬品ではないため、もっぱら医薬品と捉えられるような効果・効能を標榜することは『医薬品』とみなされ、薬機法の適用となってしまう可能性があります。
この、健康食品における【効果】の部分の言葉の表現方法がとても厳しく規制されています。
お薬(医薬品)は正しく主治医や薬剤師、あるいは専門サイトを参考に引用したりするケースが多いと思うので、感想の書き方をこれからお話する事項にさえ注意を払えばおおむね問題はないと思いますが、サプリメントなどの『健康食品』のレビューに関してはかなーり気難しくややこしくなりますので、このへんの具体的なことは別途徹底的に掘り下げてお話します。
②景品表示法
景品表示法第5条は不当な表示を禁じています。ここでいう『表示』とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示をいいます。
※第2条第4項
つまり、自分の会社の商品の紹介やレビューですね。
そのため、基本的には商品・サービスの購入者・利用者である消費者が書き込む口コミは、景品表示法上の『表示』には該当しません。
ただし、事情者が自ら顧客を誘引する目的で口コミを書いたり、あるいは第三者へたくさん口コミを掲載させたり、実際の品質よりも優良あるいは有利であるなど、消費者に誤認識させるようなものであれば景品表示法の適用となります。
とりわけ、自分(消費者)が口コミサイトに書き込みをする際には、事業者と繋がりがある【サクラ】と捉えられないように気を付ける必要がありますね。
多量の投稿や事実以上の極端な表現NG
③健康増進法
「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」
※健康増進法第65条第1項
これは消費者による口コミやレビューが、健康増進法第65条第1項で禁止されている虚偽・誇大表示にあたるかどうか、ということです。
薬機法と同様に、規制の対象について、「何人も」と定められていることから、食品の製造業者、販売業者等に限られることなく、新聞社、雑誌社、放送事業者、インターネット媒体社等の広告媒体事業者や、これら広告媒体事業者に対して広告の仲介・取次をする広告代理店、サービスプロバイダー等も規制の対象となり得ます。
SNSや個人ブログも含まれます。
例えばアフィリエイターが、広告主の販売する健康食品について虚偽誇大広告表示にあたる内容を掲載した場合に広告主がその表示内容を具体的に認識していない場合であっても、広告主が法的な責任を問われる可能性がある、ということです。
また、「著しく」の該当性は、個々の広告に即して判断がなされるもの(ケースバイケース)だそうですが、
例えば、
『大量に書き込みをしてサイトでの評価を変動・上昇させる』、
『一般消費者に多数から好意的な評価をされていると認識させる』、
『印象を強く与える、あるいは極端に高い評価をつける』、
そういった類いは「誇大広告表示」にあたるおそれがあるとされています。
こうした場合、一般消費者は『広告であると認識することができない』可能性を秘めており、その評価や表示内容が商品選択に与える影響が大きいため、規制の対象となっているのです。
誇大表示も事実とは異なるので広義では虚偽になりますよね。加えて消費者を誘引するようなことをしてしまえば、法に抵触してしまう、というものですね。
効果についてや、極端な言い過ぎNG
④医療法
平成29年医療法改正により医療に関する広告規制の見直しが行われました。同改正では、患者保護の観点から、医療機関のウェブサイト等についても新たに規制の対象とし、他方で、患者が知りたい情報(自由診療等)が得られなくなるという懸念を踏まえ、一定の条件の下に広告規制を解除しています。
規制は厳しくなったけど、それでも患者が欲している情報は誤認されることなくきちんと得られるように整備された、ということですね。
ここでいう【広告】とは、下記の3つの要件をすべて満たした場合に規制対象となります。
①誘引性(患者の受診等を誘引する意図があること)
②特定性(医師の氏名や病院の名称等が特定可能であること)
③認知性(一般人が認知できる状態にあること)
誘引性は他の法律でも同様ですね。特定性も誘引性と合わせて考えてみるとわかりやすいかもです。
たとえばSNSとかで
「◯◯病院の◯◯先生のおかげで治った!同じ病気に苦しんでいる方、是非とも受診してみてください。価値観が変わりますよ!」
みたいな投稿をみかけたりすること、ありますよね。こうした表現は①の誘引性、②の特定性、ともに該当していることがわかりますね。
3つ目の認知性とは、テレビCMとか看板もかチラシとかが対象だったそうです。誰もが目にするもの、ですね。これらは該当していた。
自由診療の美容整形外科とかは、CMで自分の病院を誘引する意図があるからCM流してるわけで、加えて勿論のこと自分の病院を特定してますね。そしてCMなので誰もが目にするものですね。
3つ満たしていますが、法律上【患者が知りたい情報(自由診療等)】に関しては一定の条件の下に広告規制が解除されているので、虚偽とかよっぽどの誇大広告でもない限りは問題がなく、だからCM放送ができるんですね。
そして、認知性に関してはウェブサイトなど患者が自らの意思で情報を求めて検索する能動的な閲覧であることから認知性の要件を満たしていないので該当せず、規制の対象外なので問題なかったのですが、平成29年の規制の見直しによってインターネット上のサイトもすべて規制の対象となりました。
つまり、SNSやブログも対象です。表現の仕方によっては『医療広告』とみなされます。
例外として、通常、医療広告とは見なされないものとして、学術論文・学術発表等、新聞や雑誌等での記事、患者等が自ら掲載する体験談・手記等、院内掲示・院内で配布するパンフレット等、医療機関の職員募集に関する広告が挙げられます。
これらは原則として上記の「誘引性」の要件を満たしていないため、広告に当たらないとされています。
つまり、『SNSやブログで体験談であったりエッセイの書籍のような手記であったり、その場合は基本的には対象外となるものの、それでも上記の①と②の2つを満たしてしまったら広告に該当し場合によっては法に抵触してしまうおそれがある』、ということですね。
たとえば前の例の体験談であったり、DMを不特定多数に送りまくって特定の医療機関を受診する患者さんを増やすような行為も、誘引に該当するので広告とみなされたりする場合もあります。
ここまで挙げた法律を踏まえた上で、お薬に関してはさらに追加規制がある。
この医療法のところだけをみれば、SNSや個人ブログサイトで自らの体験談として治療や効果の手応えなど語ることはOK、3つの条件を満たすのともないでしょうーーーと思いがちですが、しかし、どうやらそう単純なことでもないようです。
次にお話します。
【広告】に該当するか否かがわかりにくい
ここまで薬機法、景品表示法、健康増進法、医療法、それぞれでたびたび出てきた虚偽・誇大表現・サクラ・顧客の誘引・特定性、このようなものに捉えられる言葉の表現はいずれの場合も用いてはいけないことはわかりましたが、【広告】という言葉ですが、どういったものが広告に該当するか、ちょっとわかりにくいですよね。
たとえば、医療法としては、体験談であればSNSやブログで好きに語ることは誘引性と特定性を満たしていなければOKではありますが、ところが薬機法では効果については語ってはいけないとありますので、たとえ個人の体験談であっても健康食品に関してはやはりSNSや個人ブログで健康食品や医薬品を使ってみた結果の効果については語ってはいけません。
ここの【『医薬品』と『健康食品』の区別】はしっかりと理解しなければなりませんね。
ですので簡単にまとめると、
・ありていに、どんな媒体であろうと特定の商品について紹介したり感想を述べたりしている時点で、その投稿は広告に該当し、SNSも個人ブログも含まれる。
・そのためSNSや個人ブログも様々な法律による規制の対象となり、表現方法によっては違法となる。
・しかし、広告になることそのものがやってはいけないことというわけではなく、法律で認められた文言・表現を用いる限りは法律に抵触することはない。
ということになるのではないかと思います。
つまり、
●健康食品等のレビューの場合
【サクラと捉えられないよう注意しつつ(景品表示法)、虚偽・誇張をしないよう誇大な表現をせず(健康増進法)、改善・治療・効果といった文言を一切使わずに(薬機法)、レビューを投稿する。】
⚠️『効果・改善』は絶対NG!
●医薬品のレビュー(治療の感想)の場合
【サクラと捉えられないよう注意しつつ(景品表示法)、さらに特定の病院や医師への誘引・煽動とならないよう強調しすぎないよう誇大な表現をせず(医療法)、同様に医薬品そのものの効果を虚偽・誇張せず(健康増進法)、自分自身の結果のみの場合に限り『改善・治療・効果』といった文言の使用がOK(医療法)、レビューを投稿する。】
⚠️自分の体験の範疇であれば『効果・改善』を語ってOK!
という具合になるかと思います。
普通に、下心なく、悪意なく、純粋に、まともに常識の範囲内でSNSやブログをやっている限りでは、そうそう抵触するようなことはないと思います。
しかし、薬機法の中でもとりわけ『効果・改善』に関してだけは本当に厳しく、難しく、知らず知らずのうちに違反してしまっている場合があるので、きちんと勉強し直して、表現方法にはしっかり注意する必要がありますね。
大抵の方がそうかと思いますが、こういうのは法律の専門家しか真に正しいことはわかりません。
正直、理解しきるのは難しく、当ブログも完全に正しい表現で運営できているか定かではありませんし、調べれば調べるほど不安が募るばかりですが、できる限り誠心誠意、誤りのないように運営していきたいと心がけております。
この記事の作成にあたっては、
モノリス法律事務所さんの、
を参考に学ばせていただきました。
もし不適切な表現がありましたら適切に訂正・削除致します。
次回は引き続き法律と広告のお話。広告についてはもっと深く掘り下げてお話していきたいと思います。
カテゴリー『個人ブログサイトで健康食品のレビュー等を行う際に知っておくべき法律と注意すべき表現のまとめ』はコチラ↓

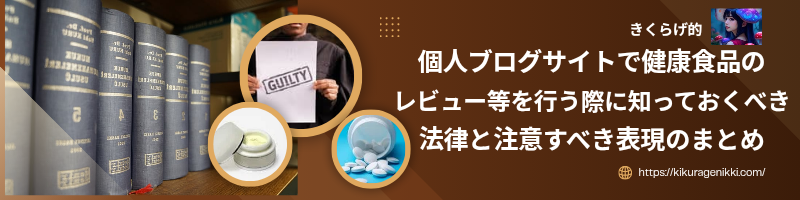
コメント