前回の最後に薬機法第66条における『広告』について少し詳しくお話しましたが、今回はもっと掘り下げてお話していきます。
深く理解しないと知らず知らずにアウトなことをしてしまっている、なんてこともあります。
私個人のことですが、私クローン病という難病を持っており、SNSや当個人ブログサイトなどで体験談など投稿したりしています。
法律が厳しくなってきている中で、正しいことを理解しようと努めておりますが、素人ですのできちんも理解できずにいるため、最近益々なにも発言・表現ができなくなってしまいました。
ですので、こうして日々調べてはまとめているわけですね。
理解を深めて適切な表現を心掛けていきたいと常々思っております。
では今回は『具体例』を挙げつつ、なにがどう違ってて何がセーフで何がアウトなのか、みていきたいと思います。
ここはしっかりと理解できるようにしましょう。
①医療法について:例
前提として【医師による適切な診断と処方による治療を行っている】として、
同じ病気の方たち同士SNSで、
「治療薬をAからBに変えることになったのですが、Bを使ってる方いましたら効果とか副作用とか、どんな手応えとか教えてください」
という質問があって、
「私は投与◯回目あたりから炎症反応が下がってきました」
「活動期から寛解期にまで回復しました」
ですとか、こうした【効果】についてコメントをし合うことが多いです。
心配になるのは、
法律によって虚偽・誇張など明らかに倫理から外れ、患者・消費者に誤解を与え健康を脅かす恐れがあるよう投稿は法に抵触することは理解していますが、【個人の体験談としての効果の投稿】は果たして法律に抵触するのかどうか。
です。
こういった場合は、【医療】ですのでわあくまでの個人の体験談に限りOKと判断されると予想されます。
虚偽・誇張もなく、特定の病院や医師の誘引もなく、オススメ!とかもなく、処方に関することなので体験談はそもそもOK。
という角度からセーフと思われます。
※あくまで、きくらげ判断。ご自身でしっかり調べてください。
また、
「◯◯な状態がずっと続いてて、だんだん悪化してきてるんですけどどうしたらいいでしょう?」
「市販薬の◯◯とか買って飲んでもいいですかね?」
などの質問もよくあります。
こうした質問に、
「病気Aとか病気Bとかも考えられますし、きちんと病院へ受診したほうがいいと思います」
「自己判断は危険ですので主治医と相談したほうが望ましいと思います」
といった返答は、病院への【誘引性】に該当するか否か。
よくあることですよね。
この場合、まず病院や医師を指定していないので『誘引性』には該当しないかと思われます。
「なんか不調あったら病院にいきしょう」、これ自体はなにも問題ありませんよね。
病気に関しても素人でありながら病名を特定したりもしていません。
様々な可能性があるからきちんと受診しましょうね、というお話なのでセーフです。
こうして例でみてみますと、通常の会話で抵触することは少ないのではないかと個人的には思います。
が、たまーに、ゴリゴリと
『◯◯病院の◯◯先生へ!!』と激推ししたり、
『そんな病院ダメだ!』と全否定したり、
『その治療は間違ってる!』と否定したり、
そうした投稿も見かけますよね。
言いたいことはわかります、が、表現方法に問題があります。
たとえば、「その治療法は適切かどうか、他の可能性もあるかもしれませんし、セカンドオピニオンをお勧めします」とかでしたらセーフになるかと思います。
『可能性』を示唆することが重要で、素人判断で可能性を潰して『間違いだと断定』してはいけません。
だって、医師じゃないんですから。
こうした断定言葉は『過度・過剰・誇張』になりかねませんので、言いたいことを伝えるにしても言葉選びはやはり大切です。
②健康食品について:例
健康食品については主に薬機法に留意する必要があり、虚偽・誇張をしてはならないことは勿論、医薬品と捉えられるような【効果】の表現はしてはならないことは私自身も理解しております。
【改善・治った、治す】、のような文言は効果の保証をする表現であり、こうした表現は誤解を与え健康を脅かす恐れがあるのでNGです。
また、66条において『何人も』とあるので、SNSや個人サイトでの体験談であろうと、どんな媒体であろうと、法の適用範囲であることも理解しましょう。
『個人の感想です』という言葉を添えたとしてもNGです。
しかして個人的に難しい思うのは、やはり難病者同士でSNSで健康食品(サプリメントなど)の個人の体験を元にした質疑応答は多々あります。
例えば、下痢や下血をしやすい疾患ですので、お腹の調子に作用する健康食品や、
虚弱な体質でもある疾患なため、体力を増強する作用のある健康食品、
口内炎をできにくくする健康食品など、
栄養機能食品や機能性表示食品、特定保健用食品などの情報交換はとても多いです。
こうした健康食品の個人が体験した効果として、
「◯◯を飲むようにしてから下痢が減った」
「体重が増えてきて体力ついてきた」
「疲れが回復しやすくなった」
など、SNSや個人サイトではこうした個人の【具体的な効果の体験談】が横行しております。
また、エッセイ本などにも具体的な個人の効果について記載されているものも多いです。
難病情報誌では患者さんの体験談などのコラムがあり、そこでもやはり個人の体験として効果のお話は必ずといっていいほど出てきます。
私自身もとくに意識せずにやっておりました。
健康食品は医薬品ではないので効果については言葉の表現に厳しく制限があるはず、と調べていて把握したのですが、現実、SNS、個人ブログ、エッセイ本、情報誌など、昔と変わらず効果のお話はあります。
『みんなやってるからOK??』
そんなことはありません。原則NGです。
体験談として効果を語って良いのは医薬品だけですので、健康食品に関してはどんな媒体でもNGです。
※書籍(エッセイ本でもNGですが、表現方法によって抜け道があり、そこには監修も必要で、販売されている多くの書籍はこうした問題をクリアしています。
個人同士でやり取りするSNSでは当然のこと監修はありませんので、たいていNGです。
コロナ禍で誤情報が拡散したことは記憶に新しいかと思いますが、当然すべてNG。
ですが、行政としてはすべてを取り締まることは現実不可能で、注意喚起に留まっています。
ブログサイトトップランカーは大衆に与える影響が大きいので規制されやすかったりもしますが、細々とやってる限りではそうそう違反でしょっぴかれることはありません。
ですが、ダメなもんはダメなんですよ、ということは理解しておきましょう。
マンガとかの二次創作と似てますね。本当はブラックだけど現状グレー、みたいな。
とにかく、違反は違反なので、やはり、これらはみな違法であり、SNSや個人ブログサイトであっても厚生労働省が公開している置き換え言葉で表現するように高い意識を持ちましょう。
たとえ、誤情報を流布する意図はなく、営利目的でもなく、純粋に情報交換のつもりでやっていることでも、法律もどんどん規制が変化していっているので、正しく理解し正しくやっていきたいと真摯に思っていても、言葉1つでアウトになる。それが法律です。
ただ調べれば調べるほど、素人ですので言葉の自由度がどんどん低くなり、語り合えなくなってきてしまい、困りますよね。
法律家でない私たちにとっては不自由でフラストレーションたまりことではありますが、致し方ありませんね……。
そもそも広告ってなに?体験談も広告なの??
私もきちんと調べなければ理解できていませんでした。
単純に広告掲載しているか否か、というようなことではなく、
①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
③一般人が認知できる状態であること
この3つを満たしている場合、『広告』に該当するそうです。
たいがい広告になっちゃいますね……
②③は、どうしても紹介する際に記載することになるし、グレーなあたりは①ですけど、誘引する意思や意図はなくてもそう捉えられたらそれまでだし、勿論「オススメ!」とか使ったら明らかに誘引してますけどね。
でも体験談ですから、SNSなどで「これ使ったら良くなったからオススメ!」なんて、ついつい簡単に投稿しがちですよね。
ダメです。
どうしてこんな規制があるの?
なんでこんな法律があるかといいますと、ありていにいうと【消費者の安全と、消費者が誤認識することなく自主的で合理的な商品の選択ができるようにする目的】ですね。
誤情報の拡散は消費者の不安という気持ちを煽り、誤った行為への扇動となり、安全性が脅かされます。
『自主的で合理的な商品が選択できるように』、というのは、たとえば「これを飲めば感染しない!」とか、「これを飲めば治る!」とか、そうした誤情報が拡大化したら、消費者の思考から他の選択肢(本来の正しい医療を選択する考えなど)を奪い、流布された誤情報一択にしかねません。
とても危険なことです。
そのため、薬機法によって伝え方は厳格に定められているわけです。
前回のおさらいになりますが、コロナが大ブレイクしたとき、誤情報が拡散されまくったことは記憶に新しいと思います。
なんの確証もないのに見たヒト、読んだヒトを信じこませて危険な行為をさせてしまうおそれがある、そうした内容を記事などで発信し広告・宣伝・流布することはしてはいけないことなのです。
じゃあなんでコロナのときあんなに誤情報が拡散されたの?
これは薬機法の適応がSNSやクチコミサイト、個人のブログサイトなどは甘々だからなのです。
※ただし、開発者や企業などが広告をするのはNGです。
つまり、SNSやクチコミ、口頭での意見交換などは一人一人のモラルに委ねられているわけですね。全員は取り締まれない。そのため、厚生労働省や消費者庁も注意喚起までしかできないので、拡散されてしまうことがあるのです。
すごく難しい問題ですね。
個人のブログサイトも範囲内であり、とくに広告収入を得ているようなサイトでは場合によっては違反となることもありますので注意が必要なのです。
次回は薬機法について、もっと深く掘り下げてみていきたいと思います。
関連記事はコチラ↓
カテゴリー『個人ブログサイトで健康食品のレビュー等を行う際に知っておくべき法律と注意すべき表現のまとめ』はコチラ↓
個人ブログサイトで健康食品のレビュー等を行う際に知っておくべき法律と注意すべき表現のまとめ

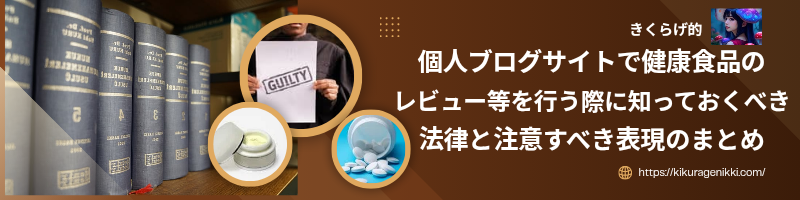
コメント