さて、広告だけが問題になるわけではありません。広告になるならないだけでなく、禁止されている用語や表現がたくさんありますので、まずこの薬機法第66条の内容について、他にはどんな項目があるのかな?もう少し詳しくお話します。
続けて健康食品について基本的なことをお話しますので、目次から好きなところにスキップしてください。
①【虚偽】や【誇張】はNG
嘘は勿論アウトなことはわかりますよね。その他にもその商品が公表していること以上の効果があるような表現、たとえば「治った!」ですとか「めっちゃ効く!」ですとか、効果を確証するような表現はNGです。
お薬ですらない健康食品や化粧品などではとくに『治る』という表現は不適切です。そもそも治療目的として作られていない・治療目的で登録、認可されていないわけですから、こうした表現は虚偽や誇張になります。
化粧品での例としては、
『アンチエイジング』、『◯◯歳若返り』→アンチエイジングはNG。若返る確証なんてあるはずもなし。
『小顔効果がある』→これも確証がないからダメ。
『ニキビが治る』→化粧品は薬ではありませんし治ると謳うことはNG。
②体験談・レビューで語るのはOK?
体験談やレビューで使用感を語ることそれ自体には問題ないのですが、そこで用いる言葉の表現には違反となる場合があります。
それは、【効果の保証】と捉えられる表現です。
『髪や肌や体調に何かしらの変化があった』→『効果があったことを意味している表現』で記事を書くことによって、閲覧者さんにあたかも『効果が得られる』という確信を与えてしまうおそれがある、またあるいは『誰でも安全なんだ』という誤解を与えてしまうおそれがあるためです。
効果には個人差があり、副作用のおそれもあるため、安全性が確実であるかのような表現や確実な効果があるかのような表現は違反となります。
よく『個人の感想です』なんていう注意書きがあったりしますよね。
私も用いています。
この文言を付け足すこと自体には何も問題はありませんが、しかし付け足したからといって法から逃げられる、というわけでは決してありません。逃げ道はありません。予防策は【不適切な文言・表現は使わない】、それのみになります。
体験談やレビューで使用できる文言としては、手触りや食感などのテクスチャーや、どんな香りがするかですとか、使いやすい使いにくいですとか、飲みやすい飲みにくいですとか、『効果』と『安全性』とは関係のない事柄であれば感想を記載することは可能です。
例えば
「香りが良かった」、「ベタベタしなくて使いやすかった」、「苦味が少なくて飲みやすかった」などはセーフ。
「肌にハリが出た」、「ニキビが治った」、「安心して使える」などはアウトですね。
体験談やレビューでも自分が使ってみた手応えとして効果について語ることはできないというのは、ちょっとモヤモヤしますけれど、やはり責任問題がありますからね。閲覧者さんに与える影響を考えれば仕方のないことですね。
③ビフォア・アフターの写真
②と同じように効果や安全性の証明になるような画像の掲載もNGです。
手応えがあったらつい載せたくなってしまいますよね。
画像を掲載することは見たヒトにとってわかりやすくて親切で丁寧で、良いことのように感じますが、でも、やはり誤解を与えてしまうのでダメなんです。
④記載してもセーフなものもある
薬機法で認められてる表現というのがあり、それらであれば体験談やレビューで用いても法に抵触しません。
ただし、注意が必要なのは、記載しても良いのは【基本情報の紹介文として効果や効能を記載することは可能】ですが、【体験談として効果があったことを記載することはできません】。
ここは法律で認められている効果であっても変わらずNGです。
どんな場合でも、「効果あったよ!」って流布しちゃダメということです。
『商品説明』と『使った結果』は別、と覚えておきましょう。
言葉として使っても良い効果効能の表現には厚生労働省の『医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等』の医薬部外品の効能・効果の範囲で表にて確認ができます。
ここに記載されている文言は、言い換えができるものもあります。
例えば化粧品であれば、
【肌を整える】と記載されているものは、『肌のキメを整える』、などの言い換えはOKです。
しかし、『肌質が改善する』、『肌荒れが治る』、『肌荒れから卒業』、などの表現は言い換えとはいえません。まったく別の意味になります。
改善や治る、と捉えられる文言は基本NGですね。改善するとも治るとも限らない商品ですからアウトなんです。
なにがセーフで何がアウトかは、詳細なことは、
を参照しながら記事を作成するのが望ましいですね。
言葉遊びのようですが日本語の難しいところで、どう解釈されるか、そこが問題なんですよね。少しでも誤解を与えるような表現はしてはならないというのは本当に難しいです。
サプリメントなどの販売をしているサイトでは、しばしば体験談などが載ってたりしますよね。その内容の中には効果を謳う内容もあったりします。
本来、薬機法的にはアウト、なんだと思います。摘発されたら逃げられないんじゃないかなと思う。果たして逃げ道があるのか、それも素人にはわかりませんが。
先述しましたが、企業であったり、広告収入を得る収益金されたブログサイトなどでは表現が厳しく制限されますが、非営利のSNSやクチコミサイト、個人のブログサイトなどでは薬機法の範囲内ではありますが影響力として低い傾向にあるためチェックが甘く、ほぼ自由にレビューを記載することが可能な状態となっています(やっていいわけではない、やっちゃダメだけどやれちゃう現状という話)。
しかし、このご時世、いつなにで問題になるかわかったもんじゃありません。
私自身も注意を払ってはおりますが、完璧であるという自信はまったくありません。
もしかしたら不適切な表現があるかもしれません。
ですので、原則をしっかりと留意し、効果や安全性に関しましては商品に正しく表記されている内容に留め、それ以上のコメントはなるべく避けさせていただきます。
サプリメント等を使用した感想に関しましても適切な表現を用いるよう心がけていきますが、それでも不適切な表現などが発覚した場合には速やかに削除していきます。
おうちとかでもダメなの??
たとえば家庭内とか、親しい友達とか、口頭で
「どっかイイ眼科知らない?」
「◯◯医院はすごく丁寧だしイイよ!」
とか、
「◯◯整形外科はダメだよ、あそこはろくに患者の話も聞いてくれないから」
とか自由にお話しますよね。
法律に抵触するのは、『誰の目にもとまる場』での言葉の表現ですから、家庭内などで口頭で話す限りは、よっぽど扇動的であったり押し付けであったり大きな誇張などでなければ問題にならないのかと思います。
しかし、SNSやブログは、誰の目にもとまる場ですので、体験談であっても言葉・文言・表現には規制がある、ということですね。
でも、たとえばレミケードとかどうなんでしょうね?
体験談として、
「レミケード6回目、炎症反応が下がってきた」
ですとか
「レミケード8回目、外瘻が小さくなってきた」
など、効果のお話はしますよね。しなきゃその記事書いてる意味がない。
効果について具体的に触れてるからアウト?
セーフ、なはずです。医師の処方による医薬品の効果については、当人の体験談に限っては効果の有無を語っても良いとされているので、『私の場合は効果あった』といった投稿はセーフです。(のはず)
こうしたことをまったく具体的に語れなかったら、やはり闘病ブログをやっている意味は皆無になりますので、法律的にセーフなのかアウトなのか素人の私には判断が難しいところも多々ありますが、
私個人としては、
『医師による適切な診断と処方で行っている私個人の治療体験談では、治療を行った結果・効果の感想は正直な言葉・文言・表現でお話させていただきます。』
ただし、あくまでも私個人の場合のお話に留まります。
治療に関しましてはどんな方も必ず主治医との相談の上、適切な診断と処方を受けてください。
健康食品について理解を深めよう
ここまで薬機法を主軸に様々な規制のお話をしてきましたが、続けてその中でも『健康食品』に関してのお話です。
ブログサイトで用いることができる表現のお話だけではなく、そもそも健康食品とは本来どういうものなのか?消費者本人の健康と安全のためにも是非しっかりと理解をしていただきたいと思います。
こちらの記事では正確性をとくに重視しているので消費者庁のHP
厚生労働相:栄養や保健機能に関する表示制度とは
より一部引用しています。
いわゆる「健康食品」とは
いわゆる『健康食品』と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。
そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした『保健機能食品制度』があります。
※消費者庁HPより抜粋
ここで、どうしても勘違いしている方が多いのは、「健康食品で◯◯を治す」のように、改善・治療のための食品だと勘違いしている消費者がとても多いです。
健康食品とはあくまでも食品であり、医薬品ではありません。健康の維持・増進に役立つものであり、改善・治療を目的としたものではありません。
言葉遊びのようですが明確に違います。
病気の予防、診断、治療を目的としていない、これが絶対です。
『健康増進』とはイコール『改善・治療』では決してありません。
病気を改善したり治したりするような効果は確認されていませんし、そのため表示される文章の表現にも一切、改善・治療を意味する文言はありません。
サプリメントも健康食品です。医薬品ではありません。そのためサプリメントであっても改善・治療を意味する文言は表示することができません。
このへんのところはしっかりと覚えていただきたいです。
保健機能食品精度って??
保健機能食品制度とは、たとえば「おなかの調子を整えます」、「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)食品の場合にはその機能について、また、国の定めた栄養成分については、一定の基準を満たす場合にその栄養成分の機能を表示することができる制度です。
繰り返しますが【機能性の表示ができる食品】です。表示ね、表示。機能と表示。ここが一般食品との違いで、後述する重要なポイントです。
保健機能食品にはどんなものがある?
みなさんも名前はご存知かと思います。
①栄養機能食品(自己認証性)
②機能性表示食品(届け出制)
③特定保健用食品(個別許可制)
それぞれ詳しく説明していきます。
①栄養機能食品
特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示する食品です。
【国の規格基準に適合した食品】で、基準に適合していれば表示するのに届け出や認可の必要はない食品です。
しかし勘違いしてはいけないのは、栄養成分とその栄養素がもつ機能の表示に留まり、その効果を謳うことはできません。
簡単にたとえますと、
栄養成分【ビタミンC】、機能【抗酸化作用を持つ栄養素です】、ここまではOK。ですが【シミが治る】、【若返る】などといった『効果(ようするに使ってみた結果)』を謳うことはできない、です。
補給はあくまで補給でしかなく、【機能=効果、ではない】。
抗酸化作用がある栄養素だからといってシミが治ると効果を確約できるわけはない、ということです。だからそんなことは記載表示できない。
ここを誤認識しないように。
消費者側は、
「ビタミンCの栄養機能食品だからシミに効くんだ!アンチエイジング!」
という解釈はしてはいけませんし、そう流布してもいけません。商品はそんなこと謳っていません。
コチラ、栄養機能食品のパッケージ表示例です↓とてもわかりやすいです。

※消費者庁HPより引用
②機能性表示食品
事業者の責任において、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づき表示した食品です。
【機能性をわかりやすく表示した食品】で、こちらは国への届け出が必要になります。認可の必要はありません。
しかし、表示には厳格なルールがあります。
届出表示、1日の摂取量の目安、摂取方法、届出番号、消費者庁届出情報の調べ方。これらを明記しなければなりません。
栄養機能食品よりも複雑ですね。とくに届出表示は勿論のことですが、1日の摂取量や摂取方法、そして機能の表示、これが重要です。
どれくらいの量をどうやって摂取したら安全なのか。また機能があるのか。
たとえば摂取量と摂取方法を明記した上で「お腹の調子を整えます」といった機能を謳うことができます。
栄養機能食品よりももう一歩確かな文言が表示できますね。
これも間違えてはいけないのは「下痢を治します」はNGですのでそう表示されている機能性食品はありません。機能性食品も、健康食品であるため改善・治療を意味する文言は使ってはいけません。
消費者側も、
「機能性食品で『お腹の調子を整えます』って書いてあるから下痢が治るはず!」
と解釈してはいけませんし、そう流布してもいけません。商品はそんなこと謳っていません。
③特定保健用食品
一番耳に馴染みのあるでしょう『トクホ』です。
身体の生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。
【国が個別に許可を認めた食品】で、安全性や有効性に関する審査を受け、許可を得られた食品だけが表示することができます。(健康増進法第43条第1項)
許可された食品には、許可マークが表示されています。
消費者側にはあまり関係ありませんが、特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)
【用途の表示】とは、「コレステロールの吸収を抑える」ですとか、「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」など商品の用途・目的、その表記です。
機能性食品よりも一層具体的な作用を明記できますね。
しかし、やはりトクホでも変わらず同じなのは、あくまでも健康食品なので改善・治療目的ではないということ。
そのため、他の保健機能食品と同様に「コレステロール値が下がる」ですとか、「中性脂肪の値が下がる」ですとか、改善する、治る、といった表現を用いることはできませんし、そう表記されている商品もありません。
消費者側も、
「これはトクホだしコレステロールの吸収を抑えるって書いてあるからコレステロール値が下がる!」
と解釈してはいけませんし、そう流布してもいけません。
一言まとめ
しつこいほどに繰り返しましたが、健康食品は食品であるということ。
【健康に役立つ機能(作用)があっても、必ずしも効果(改善)があるわけではない。何故なら食品は食品にすぎず、治療を目的としたお薬ではないから。】
この一文をしっかりと覚えておいてください。
誤認識してしまい、過剰摂取をしてしまい、健康を損なってしまう場合がしばしばあります。
そうした結果は、商品を生産した側が意図するものではありませんし、そうした問題が起きないよう厳格なルールに則り正しく表記されています。
自分自身の健康と安全のためにも、消費者として表記はしっかりと読み、正しく理解し、適切に摂取する必要があります。
次回からは、こうした健康食品の使用感・レビューなどを投稿する際の注意として、具体例を挙げながら【総まとめ】をしていきたいと思います。
関連記事はコチラ↓
カテゴリー『個人ブログサイトで健康食品のレビュー等を行う際に知っておくべき法律と注意すべき表現のまとめ』はコチラ↓

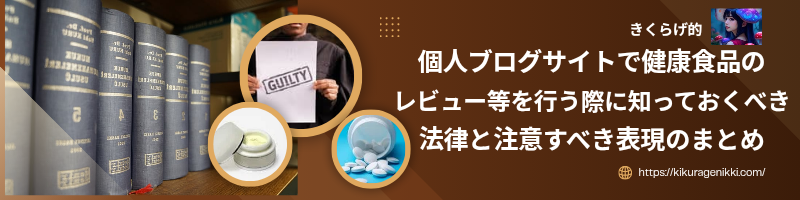
コメント