さて、ではどんなお薬で治療していくのか、内服薬の種類と効果について具体的に説明していきたいと思います。
前回のお薬の名前の記載を踏まえた上で、『商品名(先記載):一般名(後記載)』で治療薬の説明をしていきます。
※なるべくコンパクトにまとめましたが、それでも長く小難しい説明になります。ゆっくり読み返してくださいませ。
『5-ASA製剤(5-アミノサリチル酸)』
『サラゾピリン』:サラゾスルファピリジン(錠剤)
『ペンタサ』:メサラジン(錠剤・顆粒)
このお薬は主に軽症(~中等度)のIBDで小腸から大腸にかけての炎症を抑えるために用いられる『標準治療薬』です。
効果としては、5-アミノサリチル酸には炎症細胞から出る細胞に傷害を引き起こす活性酸素を除去し、ロイコトリエンという炎症を引き起こす物質がつくられるのを防ぐ効果があり、炎症の進展と組織の障害を抑制し、腹痛や血便などの症状を改善します。
ただしこれ単体での効果は高くないので他のお薬と併用していくことで効果を高めます。
また安全性が高いことから、軽症から中等度の寛解導入・活動期だけでなく、すべてのステージで服用し、寛解期では維持目的として服用を続けます。
薬の使い分けですが、ちょっと難しい話になりますが、抗炎症作用をもつ5-アミノサリチル酸は、病変部位に直接働くことで、効果を発揮します。
しかし、大腸で抗炎症効果を発揮させるには、これをうまく大腸まで届ける必要があります。
『サラゾピリン』は、5-アミノサリチル酸が小腸で全て吸収されてしまわないよう5-アミノサリチル酸とスルファピリジンが結合した構造にすることで、大腸まで運び、結合部分は大腸の腸内細菌により分解させることでちょうど大腸で有効成分の5-アミノサリチル酸が切り離されて効果を発揮するように出来ています。
ただし、大腸で抗炎症作用を発揮することから、潰瘍性大腸炎・大腸型クローン病には有効ですが小腸型にはあまり向きませんので、小腸型クローン病は医師によっては処方しません。
これに対し『ペンタサ』は特殊なコーティングによって溶ける時間を調整したもので、徐々に溶けて小腸・大腸ともに有効成分を放出します。
ですので小腸・大腸型クローン病の場合ペンタサを処方されることになります。
『チオプリン製剤(免疫調節剤)』
『イムラン』:アザチオプリン(錠剤)
『アザニン』:アザチオプリン(錠剤)
『ロイケリン』:6-メルカプトプリン(散剤)
このお薬は免疫の働きそのものを抑制することで、腸の炎症を下げる効果があります。
元々は臓器移植等でも拒絶反応を抑制するためのお薬でしたが、免疫の異常(自己への攻撃)を抑制する目的としてIBDでは使われます。
症状が中等度の場合や炎症が持続している場合に使用されることが多いです。また、手術後の再燃予防としても使われます。
炎症が下がることで下痢や腹痛も治まっていきますが、治療効果はゆるやかにあらわれますので長期的に服用することになります。
副作用として腎臓に異常が顕れないか少量の服用で血液検査をして確認してから増量して一定の量と期間服用します。
『アザチオプリン』は体内で6-メルカプトプリンという物質に変わり、免疫を担当するリンパ球の合成を阻害します。最終的に6-メルカプトプリンがさらにさまざまな酵素により分解され、その分解された有効成分が炎症を抑えると考えられています。
標準治療薬のメサラジンやステロイド製剤で効果が不十分な場合、あるいはステロイド製剤を減量したい場合や、生物学的製剤(後述)の効果を高めるなどの目的で使用します。
また長期維持療法にも有効なので、寛解期でも維持目的として服用を続けることもあり、寛解導入・寛解期・活動期どののステージでも服用します。
『ステロイド製剤』
『プレドニン』:プレドニゾロン(錠剤)
『水溶性プレドニン』:プレドニゾロン(注射剤)
『ゼンタコート』:ブデソニド(カプセル)
このお薬は副腎皮質ホルモンの一種で、強力な抗炎症作用を持ち、炎症性、免疫系、アレルギー性の病気などに幅広く使用されており、IBDにも多く使用されます。
クローン病では活動期の中等症・重症の患者さんに対して投与されます。主に5-ASA(アミノサリチル酸製剤)で十分な効果が得られない場合や、中等度以上の強い炎症を抑える場合に用いられます。
導入と離脱・副作用などの多くの懸念要素があり、長期服用すると様々な副作用が発現する可能性が高いことから、使用には慎重になります。
症状の改善に伴い徐々に減量する(離脱)ことが重要です。
ちょっと怖いかもしれませんが、慎重に判断していくのは医師ですので、よく相談しながら上手くコントロールすれば副作用は最低限に抑えることが可能です。
また、近年、とても副作用が少なく、離脱もしやすい新しいタイプのステロイド製剤も発売され導入されています。こちらは別途詳細を説明しますね。
※お薬情報参考元:IBDプラス/クローン病の治療で使用する主なお薬一覧
お薬を受け入れる
これら内服薬は、ステージによって服用するお薬も量も変わってきますが、無事に活動期から寛解期へと導入てましたとしても、お薬がなくなることはありません。
今度は寛解維持目的での服用に切り替わり、ずっと飲み続けることになります。
患者さんの中には、「いつまで飲み続けるのだろう?」、「こんなに長いこと服用してて大丈夫なのだろうか?」、「将来が心配…」。
そうした声もよく見聞きします。
しかし、根治ができない以上、なんとしてでも寛解を維持しなければならないですし、将来への不安も理解できますが、今を生き延びなければ明日はないのです。
将来、お薬がいらなくなる治療は誕生するかもしれませんが、現状は受け入れるしかありません、
どうか納得してください。ご自身の身体のために。
次回、『薬物療法-②生物学的製剤とは?』に続きます。
※だんだん難しいお話になります。
カテゴリー『内科治療』はコチラ↓
サクッとクローン病治療の概要をまとめて知りたい方はコチラ↓

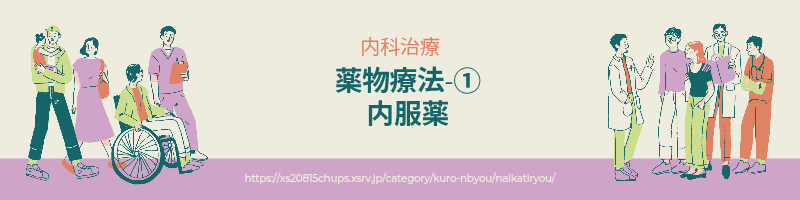
コメント