それでは、前回のレミケードの例で生物学的製剤とはどんなものか、ざっくりわかったかと思いますので、リストの残り②~⑤まで一気にご説明します。
②ヒュミラ:アダリムマブ(注射剤)
こちら効果と作用はインフリキシマブと同様ですが、『完全ヒト型抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体製剤』です。
インフリキシマブとの投与の違いは、患者さん自ら在宅で皮下注射できる点で、通院の手間が省けます。
初回→2週→4週以降は2週サイクルで皮下注射します。
クローン病患者さんって、お肉少ないですよね。私もアダリムマブを使っていた時期がありますが、肉をつまむのが結構むずかしかったです。
それと、注射針ですがこれまたなかなかに『ザ・針』です。とても濃い液体ですので針の太さが必要なことと、注入もゆっくりになりますので、糖尿病のインスリン注射のように小さくて細く、サッと済むものではありません。
最初はちょっと怖いかもしれませんね。
※私が使ってた頃と違って、現在はペンタイプでかなり細い針になってます(それでもザ・針)。
⚠️『完全ヒト型』というのがちょっとしたポイントになりまして、患者さんの中にはインフリキシマブを避けたがる方もそれなりにいらっしゃるんですね。というのは、インフリキシマブはキメラ型であるからです。
食品とかと同じように、『何由来か』という部分って、結構気にされる方は気にされます。
しかしながら、少なくとも生物学的製剤に関しましてキメラ型が劣っているとか副作用が強いとか、そういったことはありません。
むしろ、効果の程はキメラ型であるインフリキシマブのほうが高く安定している傾向にあります。
勿論、なにを使うかの判断は患者さん一人一人の判断ですが、偏見で忌避することは避けるべきことです。大切な治療ですから。
③ステラーラ:ウステキヌマブ(注射剤・点滴)
ウステキヌマブは、クローン病の主な原因物質の1つと考えられている『インターロイキン(IL)の働きを抑える』お薬です。
このお薬のターゲットはサイトカインの『インターロイキンIL-12とIL-23』で、この物質の働きを抑えることで、免疫を抑制します。
初回だけ点滴注射します。その8週間後に皮下注射し、それ以後は12週間の間隔で皮下注射を続けます。
なお、投与の間隔が8週を超えると効果が弱まるようであれば、間隔を8週間まで短くすることがあります。
投与間隔の短縮や、投与を継続するかどうかは、患者さんの症状や病気の経過、副作用などを考慮して医師により慎重に判断されます。
④エンタイビオ:ベドリズマブ(点滴)
こちらは、2019年5月よりクローン病に対しても使うことができるようになった新しいお薬です。
このお薬は白血球の一種であるリンパ球が腸粘膜へ入り込んで引き起こす炎症を抑えつつ、腸以外への影響は少なくなるように開発された生物学的製剤です。
ターゲットは消化管の炎症において重要な役割を担っている『α4β7インテグリン』というタンパク質です。ベドリズマブはこのα4β7インテグリンに対して働く抗体を精製した生物学的製剤で、α4β7インテグリンと結合しTリンパ球の遊走(腸への移動)を抑えます。
初回点滴注射→2週→6週に投与し、それ以降は8週間の間隔で点滴注射を続けます。
※3回以上投与しても効果がない場合、この薬を継続して使用するかどうかは、患者さんの症状や病気の経過、副作用などを考慮して医師により慎重に判断されます。
⑤スキリージ:リサンキズマブ(注射剤・点滴)
スキリージは、はじめは点滴で『活動期』の腸管粘膜の炎症による症状を改善して寛解状態に導き、それ以降は『オートドーザー』という器具を使った皮下注射で寛解状態を維持する生物学的製剤です。
ターゲットは、サイトカインの一種である『インターロイキン(IL)-23』で、スキリージは、このIL-23の働きを抑える抗体で、炎症を引き起こすさまざまな物質が作られないようにして、クローン病の症状を改善するします。
寛解導入療法では4週間隔で3回(初回、4週、8週)点滴静注します。維持療法に用いる場合は、点滴静注による導入療法終了4週後から、8週間隔で皮下注射します。皮下注射は「オートドーザー」という器具を用いて、医師または看護師が行います。
使い方がちょっと他のと毛色が違いますね。
⑥シンポニー:ゴムリマブ(皮下注50mgシリンジ)
完全ヒト型抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体製剤。
関節リウマチから潰瘍性大腸炎患者において適応となりました。クローン病は適応外です。
こちらはレミケードやヒュミラと同様に、TNF-αと結合することにより、TNF-αによる生体内情報伝達を阻害します。
通常、成人にはゴリムマブ(遺伝子組換え)として初回投与時に200mg、初回投与2週後に100mgを皮下注射します。
初回投与6週目以降は100mgを4週に1回、皮下注射します。
本剤の投与開始後、14週目の投与までに治療に対する反応がみられない場合には、本剤の投与を継続するべきかどうかも含め、治療法について再考します。
ヒュミラと同じく皮下注射ですが、こちらは基本的に医師が注射を行います。
治療開始後に十分な指導・手順の習得ができ、自己注射の適応が妥当と判断された場合には自宅などで自己注射をすることも可能になります。
怖かったらずっと先生に注射してもらうことも勿論可能です。
※ちなみに私はヒュミラが身体に合わなかったのでレミケード使ってますが、幸運なことに効果が切れることなく、実に10年近く長く使えています。
※お薬情報参考元:IBDプラス/クローン病の治療で使用する主なお薬一覧
駆け足ですがこんな感じです。
レミケードしかなかった昔と違い、現在は種類が豊富ですので、レミケードの効果がなくなったら後がない・・・!という心配はいらなくなりました。ありがたいことです。
最後に注意点
生物学的製剤のお話はこれで終わりです。次回は『薬物療法-⑤日常のお供のお薬』です。

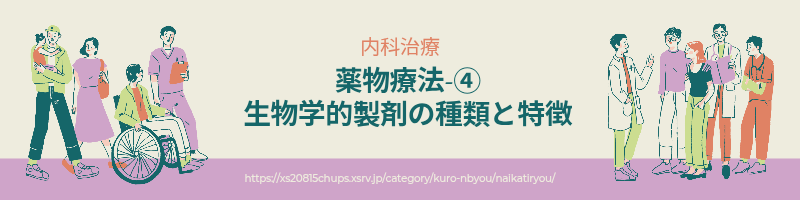




コメント