今回はクローン病と同様、5-ASAと併せて使っていくことになる免疫調節剤・免疫抑制剤について詳しくお話していきたいと思います。
こちらも、潰瘍性大腸炎のみ適応の特殊な製剤があります。
免疫調整剤と免疫抑制剤(アザチオプリンとタクロリムス)
クローン病と同様に、IBDである潰瘍性大腸炎は免疫の過剰反応による自己破壊であるため、免疫を抑制する(免疫を抑制することで攻撃力を下げる)『免疫抑制剤』が使用されることがあります。
免疫の働きを抑える作用がそれほど強くない製剤を『免疫調整剤』、作用のとても強い製剤を『免疫抑制剤』といい、区別されます。
これらは免疫の働きを抑え込むことで腸の炎症を静め、下痢や腹痛を治めていきます。
①チオプリン製剤(免疫調節剤)
『イムラン』:アザチオプリン(錠剤)
『アザニン』:アザチオプリン(錠剤)
『ロイケリン』保険適用外:『6-メルカプトプリン』保険適用外(散剤)→潰瘍性大腸炎のみ適応
主に上記の3種類があります。
免疫を抑制する作用はそれほど強くなく『免疫調節剤』と言われており、効果はゆるやかに現れ寛解導入と寛解の維持に効果を表します。
アザチオプリンは、体内で代謝され、有効成分である『6-メルカプトプリン』に変わり、効果を発揮します。
6-メルカプトプリンは免疫を担当するリンパ球の合成を阻害します。
最終的に6-メルカプトプリンがさらにさまざまな酵素により分解され、その分解された有効成分が炎症を抑えると考えられています。
主に、症状が中等度の場合や炎症が持続している場合に使用されることが多く、クローン病の場合では手術後の再燃予防としても使われます。
標準治療薬のメサラジンやステロイド薬で効果が不十分な場合、あるいはステロイド薬の減量を目的として使用するのことが多いですが、長期維持療法にも有効なので、寛解期でも維持目的として服用を続けることもあり、活動期から寛解導入・寛解期まで、どのステージでも服用します。
また、生物学的製剤を使用している場合、免疫調整剤を併用することで効果が高く、また生物学的製剤が使える期間も長くなることが確認されているため、5-ASAと共に併用する場合が多いです。
『ロイケリン』保険適用外:『6-メルカプトプリン』保険適用外(散剤)
※潰瘍性大腸炎でのみ適応されます。保険適用外の免疫調整剤です、
潰瘍性大腸炎で、標準治療薬のメサラジンやステロイド製剤で効果不十分な中等症から重症例や、難治例の中でステロイド製剤投与中は安定しているが、ステロイドの減量に伴い再燃増悪する『ステロイド依存例』(別途ステロイドのお話で詳しく解説します)の場合に使用されます。
ただし、本来は血液ガンの白血病の治療に用いられる薬で、潰瘍性大腸炎の治療に対しては保険適用外です。使用を希望する場合は、医師とよく相談しましょう。
※使えるけどとても高価ということ
②カルシニューリン阻害薬(免疫抑制剤)
この系統の免疫抑制剤は、免疫システムで重要な役割をするリンパ球に働き、カルシニューリンという酵素を阻害して免疫システムに必要なシグナルを送れなくすることで、免疫作用を抑制します。
主に2種類の製剤があります。
- 『プログラフ』:タクロリムス(カプセル)→潰瘍性大腸炎のみ適応
- 『サンディミュン』保険適用外:シクロスポリン 保険適用外(点滴)→潰瘍性大腸炎のみ適応
それぞれご説明します。
『プログラフ』:タクロリムス(カプセル)→潰瘍性大腸炎のみ適応
タクロリムスは2009年に適応となった比較的新しいお薬です。強い免疫抑制作用を持つ薬剤で、元来臓器移植等の際に拒絶反応を防ぐために用いられていましたが、潰瘍性大腸炎など難治性で重症の症例に使用できるようになりました。
ただし、こちらのお薬は血中濃度の管理が必要なため投与開始時は入院加療が必要となります。
・タクロリムスの使用方法
潰瘍性大腸炎では『寛解導入療法』として使用します。寛解維持目的では使用できません。
投与方法
1日2回、朝・夕食後に経口投与。
同じ量を内服しても人によってタクロリムスの血中濃度が大きく変化することがあるので、血中濃度の測定が必須となります。
具体的には、
- ・投与開始~2週間の血中トラフ値:10-15 ng/ml
- ・投与開始2週間以降の血中トラフ値:5-10 ng/ml
※トラフ値:薬を反復投与した際の最低血中濃度のこと。この場合、薬剤投与直前に採血をした血中濃度のことです。
血中トラフ値を見ながら内服する量を加減していく必要があります。
保険適応上、『潰瘍性大腸炎では、通常、3ヵ月までの投与とすること』と決まっており、使用期間に制限があります。
つまり、潰瘍性大腸炎の『寛解導入療法』としては使用を認められていますが、『寛解維持療法』としての使用は認められていません。
そのため、アザチオプリンへ切り替えるタイミングは、アザチオプリンは効果がでるまでに2~3ヵ月かかるため、
タクロリムスの効果が出始めた頃にアザチオプリンを導入し、
タクロリムスは使用期限内に離脱→アザチオプリンのみ継続、
という形で切り替えていきます。
『サンディミュン』保険適用外:シクロスポリン 保険適用外(点滴)→潰瘍性大腸炎のみ適応
タクロリムスと同様に、重症例で強力なステロイド治療などでも効果がみられない場合、施設によって使用する場合があります。
このお薬を潰瘍性大腸炎に使用することは、まだ保険適用外ですが、海外ではその有効性が確認されており、国内でも一部の施設で使用され、同様の効果が報告されています。
タクロリムスと同様、臓器移植時の拒絶反応の抑制や自己免疫疾患の治療のために、世界中で広く使われている免疫抑制薬です。
作用が極めて強く、重い副作用が出ることもあるため、こちらもタクロリムスと同様に薬の量が適切か血液検査で確認しながら慎重に使用します。
重度の副作用が出た場合は、迅速な対応が必要とされます。
そのため、設備の整った専門の施設でのみ使用されています。
サンディミュンには点滴と内服カプセルがありますが、潰瘍性大腸炎の治療では、点滴を短期間に集中して使用します。
※使えるけど高価で、使用できる施設もタクロリムスよりさらに限定されます。
※参考元:IBDプラス/潰瘍性大腸炎の治療で使用する主なお薬一覧
ここまでのまとめ
クローン病との違いとして、大腸へのアプローチの観点から5-ASAの種類が異なることや、坐薬や注腸剤を標準的に使用すること、そしてクローン病では使えない免疫抑制剤が使えるなど、共通点の多いIBD同士とはいえ治療がかなり異なってくることがわかったと思います。
端的に、潰瘍性大腸炎のほうが適応されてる治療法が多いです。
クローン病への適応は、まだ臨床試験中のものもあり、いずれは同様に適応となると考えられます。
これほどクローン病より多くのお薬が適応となっておりますが、クローン病と同様にこれらで寛解導入することは難しく、ステロイドや生物学的製剤、JAK阻害剤などを使用することがほとんどです。
次回はクローン病よりも多用することが多く、導入・離脱が難しいステロイド製剤についてお話きていきたいと思います。
サクッと潰瘍性大腸炎の症状・治療の概要を知りたい方はコチラ↓

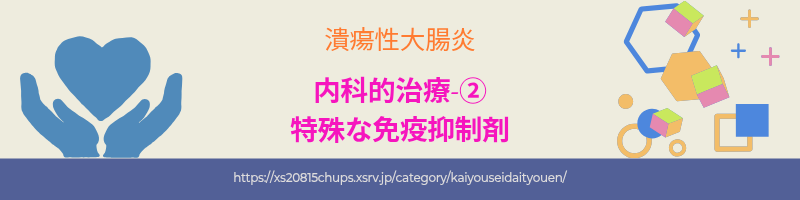
コメント