クローン病ではステロイド製剤を使うことがあまりないため、クローン病治療のお話では詳しく触れませんでしたが、潰瘍性大腸炎ではステロイド製剤を使うことが多いので、今回はそんな『ステロイド』について詳しくお話していきたいと思います。
※長文になります
ステロイド製剤とは?
とにかく効果が高い!!
昔からあり、病気をしたことがない人でも知ってるくらいポピュラーで効果の高いお薬ですね。
ステロイドとは、副腎(両方の腎臓の上端に存在)から作られる副腎皮質ホルモンの1つです。
このステロイドホルモンを内服薬や点滴として使用すると、体内の炎症やアレルギーを抑えたり、身体の免疫力を抑制したりする作用があり、様々な病気の治療に使われています。
IBD治療では、ステロイド製剤は炎症を抑える力が強く、即効性があるため、症状が激しい潰瘍性大腸炎に対して非常に有効です。 潰瘍性大腸炎では60年も前から使用されています。
多くの場合、辛い粘血便や激しい下痢といった症状が、数日から数週間といった短期間に改善します。
その高い効果から多用されるステロイド製剤ですが、認知度の高さに反しリスクがあまり知られていないこともあります。
昔からあるし安全だと思っている患者さんも少なくありません。
「効果が高くて症状安定してるのに、なんでやめなきゃいけないの?やめたら悪化しない?」
そうした声もしばしば見聞きします。
ですがステロイド製剤には副作用が多く、非常に注意が必要なお薬です。
ステロイド製剤の適応
主に5-ASAや免疫抑制剤で症状の改善がみられない中等度以上の場合に導入します。
ステロイド製剤には寛解を維持する作用はありませんので、あくまでも『寛解導入療法』のみでの使用となります。
症状の程度に合わせますと、寛解導入として
5-ASA→5-ASA+免疫抑制剤→5-ASA+免疫抑制剤+ステロイド製剤、
症状の改善がみられたらステロイド製剤は減量、離脱し、
5-ASA+免疫調整剤+生物学的製剤or血球成分除去療法などで寛解維持となります。
免疫を抑制する働きがあるため、感染症がある場合は使用できません。また、膿瘍などがある場合も増大化してしまうので使用できません。
主なステロイド製剤
- プレドニン(プレドニゾロン: 錠剤)
- プレドネマ(プレドニゾロン:注腸剤)
- ステロネマ(ベタメタゾン:注腸剤)
- リンデロン(ベタメタゾン:坐剤)
- レクタブル(ブデソニド: 注腸フォーム剤)
- ゼンタコート(ブデソニド:錠剤)→クローン病
- コレチメント(ブデソニド:錠剤)→潰瘍性大腸炎
内服薬としてはプレドニンがやはり一般的ですね。注腸剤はレクタブル以外にもいくつかあります。
プレドニンと少し違い副作用も少ないIBD用のステロイド製剤
『ゼンタコート』
ステロイド剤を遠位小腸および結腸近位部で放出するように設計された『腸溶性徐放製剤』です。クローン病での適応になります。
有効成分のステロイドの一種であるブデソニドは局所で作用する『局所作用型(腸内でゆっくり溶け出し、患部に直接作用し抗炎症作用を発揮する)』で非常に強力かつ、一般的なステロイド経口剤に比べ安全性が高いことが確認されています。
腸から吸収されて肝臓ですぐ代謝されるため、全身作用が少ないのです。
通常、ブデソニドとして3錠(9mg)を1日1回朝経口服用します。
ゼンタコート9mgはプレドニン40mg(8錠)に相当するそうです。飲む量が少ない。
また、2ヶ月程度服用し投与を終了します。
プレドニンのように8錠→6錠→4錠→…….と少しずつ減量する必要はありません。
『コレチメント』
2023年9月1日発売最新ステロイド剤!
こちらは潰瘍性大腸炎のみの適応となります。
ブデソニドを親水性基剤と親油性基剤からなるマトリックス中に分散させた素錠部をフィルムコーティングした錠剤です。
そう、5-ASAのリアルダと同じ『マルチマトリックス』ですね。
そのため、胃や小腸で溶けることなく大腸に届けられます。そして、小腸の終わりあたりからのpH変化→ph7で、フィルムコーティングが溶解し、素錠部が現れます。
これにより、大腸でのブデソニドの持続的な放出が期待されています。
ゼンタコートとの違いはどこで溶けて効果を発揮するか、ですね。まさに潰瘍性大腸炎専用です。
用法はゼンタコートと同様になります。
※参考元:IBDプラス/潰瘍性大腸炎の治療で使用する主なお薬一覧
ステロイド製剤の副作用
ステロイド製剤は高い効果と引き換えに、内服や点滴による長期投与では副腎の機能低下し、自分の副腎でステロイドを作る能力が低下してしまいます。
多くみられる副作用↓
易感染性
免疫力が下がるため、感染症になりやすいです。
満月様顔貌(ムーンフェイス)、中心性肥満
食欲の亢進と脂肪の代謝障害によりおこります。カロリー制限など食事に注意が必要です。
ステロイド薬の減量により改善するといわれていますが、実際はあまり大きな変化はなく、とくにムーンフェイスは元に戻りにくいです。
ステロイド痤瘡(ざそう)
ニキビができやすくなります。ステロイド薬の減量により改善します。
精神症状(ステロイド精神病)
不眠症、多幸症、うつ状態になることがあります。軽度のことが多いですが、よくみられます。ステロイド薬の減量により後遺症なしに改善します。
その他、増毛、脱毛、生理不順、不整脈、ステロイド筋症、などが見られることがあります。
これらがよくみられる副作用ですが、減量、離脱とともに改善します。
ストレスによって骨が脆くなり、骨折しやすくなる。
減量、離脱だけでは改善しない、適宜治療薬が必要な副作用として、
予防薬として骨を守る薬(ビスホスホネート薬)を内服する場合があります。
糖尿病(ステロイド糖尿病)
こちらも減量、離脱だけでは改善しにくい副作用です。
糖を合成する働きを高めるため、血糖が上がります。糖尿病治療を併せて行う場合があります。
その他、血栓症、動脈硬化、高脂血症、高血圧、むくみ、緑内障、白内障、なども起きる場合があります。適宜、治療薬を使用します。
また重度の副作用として、『大腿骨頭壊死(無菌性骨壊死)』が大量投与でごく稀に起こることがあります。多くの場合、ステロイド薬投与後、数ヶ月以内に、股関節の痛みで発症します。早期発見が大切です。
副作用の個人差
副作用には個人差も大きく、疾患や投与量、投与期間によっても大きく変わるため、必ずしもこれらの副作用が起きるとは限りませんが、十分に注意し、適宜対応していく必要があります。
特に注意が必要なのは、感染症、関節痛、糖尿病、骨粗鬆症ですね。
しかし、ムーンフェイスやステロイド痤瘡などは命の危険はありませんが、容姿に関わるため、自尊心への影響が懸念されます。
IBDの他に、喘息やアトピー性皮膚炎など、ステロイドからの離脱が困難な患者さんに多く、難題です。
ステロイド製剤は離脱がとにかく難しい
ステロイド製剤は導入から、症状の改善に合わせて徐々にゆるやかに減量していくことが重要になります。
離脱が難しい一番の理由に、『副腎不全(ステロイド離脱症候群)』があります。
ステロイドホルモンは副腎皮質から生理的に分泌されています。それ以上の量のステロイド製剤を長期に内服した場合、副腎皮質からのステロイドホルモンが分泌されなくなります。
そのため、急に薬を飲まなくなると、外(内服や点滴)からも内(自分の副腎)からもステロイドが体内にない状態になり、体内のステロイドホルモンが不足し、倦怠感、吐き気、頭痛、下痢、発熱、血圧低下などの症状が出現し,最悪命にかかわる場合 もあります。
これが『ステロイド離脱症候群』です。
絶対に自己判断で急に内服を中止しないように注意が必要です。
これがステロイド製剤を急に止めず、ゆるやかに減量しなけらばいけない理由です。
自分の身体でステロイドを作る機能を維持しながら減量しなければならないため、減量・離脱していくタイミングも難しくなります。
また減量していく際に再燃しやすい傾向があり、これが『ステロイド依存』という状態になります。
ステロイド依存になりますと、ステロイド製剤の離脱は難しく、症状が改善してきたら減量しますが悪化し、また増量し、改善してきたらまた減量し、すると悪化してしまうという状態となり、離脱できずに長期的に投与を続けることになってしまい、先述した様々な障害が起きてしまいます。
ステロイド依存を起きにくくするためにも、5-ASAと免疫抑制剤の併用は意味があり、副作用のリスクを下げ、減量もしやすくなるといわれています。
こうしたリスクの面から、近年ではステロイド製剤は『なるべく使いたくないお薬』で、可能な限りステロイド製剤を使用せず、『GMA(血球成分除去療法)』や『生物学的製剤』などを適宜使用し、速やかな寛解導入とその後の寛解維持ができるようにしていくことを目標としています。
しかし、それでも重症の潰瘍性大腸炎のようにステロイド製剤の導入を余儀なくされる場合もあり、治療はとても難しいです。
副作用の少ない『ゼンタコート』や『コレチメント』、『レクタブル注腸剤』などは私たちにとって福音ですね。
次回は潰瘍性大腸炎における生物学的製剤の種類と、潰瘍性大腸炎でのみ適応となっている生物学的製剤についてお話しをしていきたいと思います。

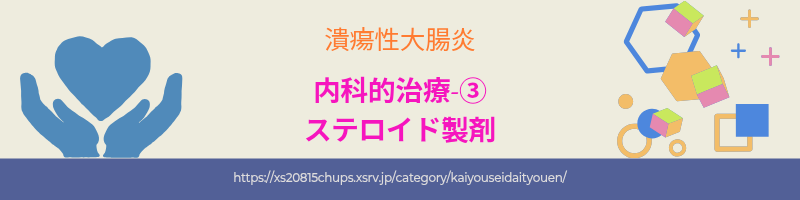
コメント