さて、クローン病疑いが濃厚となりましたら、詳細な検査をすることになります。
今回は必要となる様々な検査についてひとまとめにご説明します。
別途後述しますが、クローン病の治療には大変お金がかかります。高額な医療が必要となるためです。
3割負担では到底支払えない金額となりますが、あくまでも同じ治療を3割負担で受けたならという話で、クローン病と確定診断されたら医療費控除がありますので物凄く安く済みますので安心してください。
病気の特定が必須となるのは治療を行うためという大前提は勿論のこと、こうした特別な控除も受けられるようにするため、各種検査をし、『確定診断』を得る必要があるのですね。
では、まずはどんな検査をするかお話します。
確定診断に必要な主な検査項目
①血液検査
白血球の数(体内で闘いがあると上昇する)やヘモグロビン(潰瘍等で出血があると極端に下がる)、CRP(炎症があると上昇する)をメインに、その他の病の可能性も考慮し幅広く多くの項目数しっかり検査します。
なので採血でとる血液の量は多いです。スピッツ(試験管)5とか8本とか取ります。
「え!?こんなにとるの!?」ってビックリするかもですし、「こんなにとって貧血にならないの?」と心配になるかもしれませんが、【血が足りない】という原因で貧血になるような量では決してありませんので心配しないでくださいね。
※血を見るのが苦手な方の貧血は、血が足りないせいではありません。【迷走神経反射による貧血】という症状です。
気分が悪くなったら我慢せずに看護士に伝えてくださいね。処置室で休ませてくれます。
②検便
潜血の確認ですね。肛門や直腸に出血がありますと目に見えてわかる血便になるので自覚症状もあるかと思いますが、小腸から大腸の真ん中(横行結腸あたりまで)で出血がありますと消化酵素の影響を受けて便の色にあまり変化がみられません。
検便では見た目ではわからない潜血の確認をします。
③検尿
腎機能の確認。たんぱく質や血が混じっていないか確認します。
④胃カメラ
前段階で胃に問題が確認されなかった場合はスキップすることもあります。
胃に潰瘍がないか、粘膜の状態はどうかなどを確認します。
⑤大腸内視鏡検査
大腸内をカメラで見て状態の確認をします。クローン病にみられる特徴である『縦走潰瘍』や『敷石状病変』、『狭窄』などを細かくみます。
これらの特徴がみられた場合、『確定診断』が濃厚となります。
細胞も採取し生検に出します。
この生検で『肉芽腫』というものが確認されると、『確定診断』となります。
※肉芽腫が確認されない場合もままありますが、その他の特徴的な病変と症状によって確定的であれば確定診断となります。
※大腸内視鏡検査については、別途詳しく記事にしてありますので、よろしかったら参考にしてください。
カテゴリー『検査』はコチラ↓
⑥経管小腸造影検査
鼻から十二指腸あたりまで管を入れて、その管から造影剤を出して小腸なまんべんなく行き渡らせてX線撮影をします。
管の太さはうどんより太いくらいでしょうか。意外と細めです。
これは大腸内視鏡検査ではよく見えない潰瘍の有無と程度の確認になります。
瘻孔がありますと、そこに造影剤が入り込み、細ーい線が小腸から飛び出しているのがX線で見えます。このようにして肉眼では確認できないような病変を確認します。
造影剤には『バリウム』と『ガストロ』があり、バリウムは白くて経口でも使用可能です。また映りがとても良いです。反面、粘度が高いので細いところには浸透しにくい欠点があります。
対しガストロは透明でべたべたした液体で、経管になります。バリウムよりは映りは落ちるものの、しゃばしゃばの液体ですので細いところまで浸透します。
どちらを使うかは問診次第で医師が判断します。
検査後、管から造影剤はある程度抜きますが、残りは下からウンチで出すことになります。
⑦注腸造影検査
これは大腸の造影検査です。お尻から管を入れて直腸のところでバルーンを膨らませて栓をして漏れ出さないようにしながら造影剤を流し込み、大腸に行き渡らせて大腸のX線撮影をします。
小腸造影検査と同様です。
⑧超音波検査
『膿瘍』の有無の確認と、その他臓器に問題がないか確認をします。膿瘍がありますとしっかり映ります。
⑨その他ケースバイケースで、
眼の検査(クローン病は緑内障になりやすいといわれています)、
骨密度(クローン病は栄養障害がしばしばありますので測定しておくこともあります)、
手術を考慮して心電図や肺活量なども検査する場合もあります。
このようにあらゆる検査を徹底しますので、かなり忙しく検査疲れにもなります。
ただでさえ最悪のコンディションの中でですから、相当に大変です。
ですが初手の検査は最重要になりますので頑張りましょう。
次回は『クローン病の確定診断に至るまで③一番大事な問診』に続きます。
サクッとクローン病治療の概要をまとめて知りたい方はコチラ↓

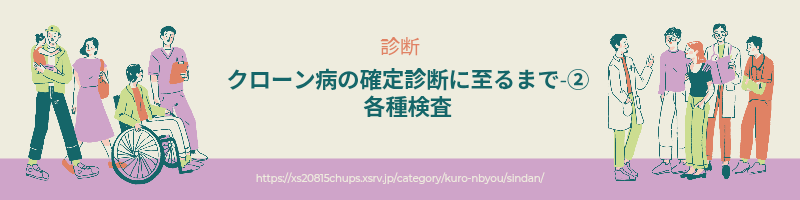
コメント