大腸内視鏡検査の実践編②、いよいよ当日本番、腸管洗浄剤の飲み方のお話です。
ここ何年かはモビプレップですが、以前はニフレックでしたので、まずはニフレックを飲むコツからお話します。
ニフレックを上手に飲むコツ
コツは2つ。
1つは、唇に液体をつけないようにカップを咥え、唇にあまり通さないように喉の奥に一気に流し込みます。
まるで錠剤を飲むときのように一息に。
ニフレックの最大の難点は量よりも味です。吐き気がかなりでやすいです。これを避けるためにはいかに味を感じさせないで手早く終わらせるか、です。
飲んだあとは唇を必ずティッシュで拭いて、できるだけ舐めないようにします。
これだけでかなり厳しさは軽減できるかと思います。
2つ目は有効な手ではありますが、現在は病院側に止められてできないかもしれません。チュッパチャプスなどを舐めながら飲む。
これはイイ手でした。
舐めて、飲む!すぐ舐める!の繰り返しですね。かなり誤魔化せます。
ニフレックに関してましてはこんなところですね。
あとは気合いしかございません。
モビプレップの飲み方のコツ
これに関しましては特にコツはございません。コップ一杯を一息に飲む。これを10分刻みでやるくらいです。
目標は速ければ速いほど良く、40分で飲みきるのが理想的です。
なので4回で飲み切るつもりですね。
※速ければ速いほどとはいっても、立て続けに飲んではいけません。吐き気がでてしまいます。10分間隔です。
そしていずれの腸管洗浄剤でも共通なことは、お腹の動きをよくしてあげることです。
お腹の動きを良くするコツ
飲み方だけでは効果的ではありません。大切なのは動くことです。
排便を促すためには腸管を動かさなければなりません。物理的刺激で促します。
足踏み、スクワット、腸揉み、ストレッチ、お尻を叩く、またあまり便意がなかったらシャワートイレの流水で肛門を刺激してあげるのも効果的です。
とにかく、飲んだら動く!!これに尽きます。
何回のおトイレで綺麗になる?
では実際どれくらいの排便回数で綺麗になる?というところですが、
これまでの私の場合ら平均ではたった4回程度です。早いときは1~2回です。
※通常ですと5~10回くらいでしょうか。もっと多い方もたくさんいます。
どうしてもちょっと汚い表現になってしまいますが、便性チェックの写真が検査準備室やトイレに貼られています。
番号で記されていて、病院により多少差異がございますが、
- ①番はまだまだ普通便。
- ②番は塊がまだ混じってる泥状便。
- ③番は塊がある程度なくなった泥状便。
- ④番は茶色い水様便。
- ⑤番は少しカスが残る黄色に近い水様便。
- ⑥番はカスがなくオシッコ並みかそれ以上に透明に近い水様便。
看護師さんが必ずチェックします。「写真の④番あたりになったら呼んでください」って指示があるはずなので、トイレにあるナースコールで看護師さんを呼んで便性のチェックをしてもらいます。
多くの方がこのチェックに大変抵抗感があります。まぁ、当然ですよね。私たちのように慣れてる患者のほうが少ないはずです。
⑤番の便性になったら看護士さんはOKをくれます。そこからは水を飲んでいれば⑥番になりますので最終チェックで合格、検査に移行できます。
患者さんの中には、ゆっくりちびちび飲む方、座って飲む方、本を読んでる方、そうした方々もしばしば見受けられます。
中には足腰が不自由であまり動くことができない方もおります。
そういった方には看護師さんが付き添い工夫して排便を促してくれますので、見栄を張らずにどっかり看護士に甘えてリラックスして排便しましょう。
長年見てきていますが、不自由がないにも関わらず動かない方々は便が出ません!あまりにも飲まない、出ないでいると看護師さんもだんだん焦ってきて語気も強くなります。
そうしますと、患者さんもイラっとして、スムーズにいかないこともままあります。
「こんなもん飲めるわけねぇだろ!!」と怒鳴り声をあげる患者さんも、遺憾ながらいらっしゃいます。
「二回でたからイイでしょう?」と言う患者さんもいます。
無理です。綺麗になるまで検査はできません。
最終的には浣腸を使い糞栓を出し、やはり無理にでも飲ませます。
不調がでて飲めない場合のみ、やるを得ずそのまま検査をする場合もあります。
ですが検査の精度はガタ落ちのため、再検査となることもあります。
辛いのはわかります。嫌々になってしまう気持ちもわかります。
ですが何より自分の健康のためなのです。患者さんの健康のために医療スタッフは常に全身全霊をかけております。そのことを理解し、受け入れ、正しく検査するために必要なことはどうかしっかりと実行してくださいませ。
次回『内視鏡検査・実践編-③検査本番!!』に続きます。
カテゴリー『検査』はコチラ↓
サクッとクローン病治療の概要をまとめて知りたい方はコチラ↓

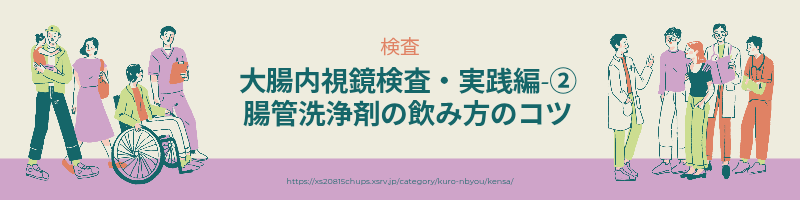
コメント