今回は潰瘍性大腸炎の内科的治療、5-ASA製剤と坐薬、注腸剤について、クローン病との差異を見ながらお話していきたいと思います。

内服薬
『5-ASA製剤』
クローン病でのお話の際には他に使う5-ASAがなかったため説明が短くなりましたが(ペンタサしか挙げなかったため)、潰瘍性大腸炎で使う5-ASAは少し機構が違うため、比較して詳しく説明していきたいと思います。
5-ASA製剤とは、メサラジン(別名:5-aminosalicylic acid、5-ASA)のことで、軽症~中等症のクローン病・潰瘍性大腸炎の標準治療薬として用いられます。
抗炎症作用があり、活動期の症状(下痢や血便、腹痛等)を抑え、寛解に持ち込む寛解導入療法や、再燃を予防する寛解維持療法として広く用いられます。
また、生物学的製剤を使う場合、5-ASAを併用することでより高い効果と持続期間が延びることが確認されているため、5-ASAはどのステージでも服用し続けるお薬です。
この5-ASAには欠点があり、小腸で速やかに吸収されてしまうため、経口投与で効率的に5-ASAを大腸へ到達させることを目的に、『ペンタサ』、『アサコール』、『リアルダ』が開発されました。
それぞれ『薬剤放出機構(薬剤が溶けて作用していくための仕組み)』が異なり、炎症箇所へ到達させるための方法も異なり、症状によって使い分けがされます。
とりわけ潰瘍性大腸炎の場合は大腸へのアプローチが重要になるため、炎症範囲が小腸型、大腸型、小腸・大腸型、直腸型と幅が広いクローンと異なり、同じ5-ASA製剤でもクローン病とは違う種類の薬を使うことが多いです。
- ①ペンタサ250mg、500mg(メサラジン:錠剤、顆粒、坐薬、注腸)→クローン病・潰瘍性大腸炎
- ②アサコール400mg(メサラジン:錠剤)→潰瘍性大腸炎
- ③リアルダ1200mg(メサラジン:錠剤)→潰瘍性大腸炎
- ④サラゾピリン500mg(サラゾルスルファピリジン:錠剤、坐薬)→潰瘍性大腸炎
5-ASA製剤①『ペンタサ』
通常1日1500mgを三回に分けて服用。活動期は4000mgを二回に分けて服用。
薬剤放出機構は、『時間依存性』で、5-ASAを腸溶性のエチルセルロースの多孔性被膜でコーティングすることですぐに溶けて小腸で5-ASAの消失されることを防ぎ、徐々に溶けて小腸から大腸まで広い範囲で放出されます。
多孔性被膜とは、小さな穴が空いている膜で、そのためゆっくり放出されることで小腸と大腸両方へ薬剤を行き渡らせることができ、小腸に病変があるクローン病にも適応であり、標準治療薬として錠剤を服用します。
ペンタサには坐剤、注腸があり、炎症範囲や症状に応じて使い分けが可能で、潰瘍性大腸炎の場合、内服に加えて坐薬や注腸を併用することが多いです。
5-ASA製剤②『アサコール』
通常1日2400mgを三回に分けて服用。活動期は3600mgを三回に分けて服用。
薬剤放出機構は、『ph依存性』で、5-ASAを高分子ポリマーでコーティングすることで、pH7となる回腸末端から大腸全域に5-ASAが放出されます。
phの低い胃や小腸では溶けず(強酸性)、phが上がりph7(中性)になる小腸の終わりからコーティングが溶けて作用するため、大腸に行き渡らせることができます。
5-ASA製剤③『リアルダ』
通常1日2400mgを一回服用。活動期は4800mgを一回服用。
アサコールより新しい薬で、薬剤放出機構は『マルチマトリックス』で、5-ASA(メサラジン)を親水性基剤および親油性基剤というマトリックスで包んだ構造の素錠部に、アサコールのようにpH応答性の高分子フィルムをコーティングした製剤です。
このコーティングによってアサコールと同様にphが7になる小腸の終わりから溶けだし、さらにゆっくりと溶けだす工夫がされているため、大腸全体に長い時間持続的に薬剤を行き渡らせます。
5-ASA製剤④『サラゾピリン』
通常1日2000~4000mgを4〜6回に分服します。
5-ASAと抗菌作用をもつスルファピリジン(SP)をアゾ結合させた製剤であり、薬剤放出機構は大腸内の腸内細菌の作用により5-ASAとスルファピリジンに分解されます。
小腸で一部が吸収され、大腸へ約90%が到達します。また,T細胞及びマクロファージにも作用して炎症を抑制することで抗リウマチ作用もします。
※副作用や服用量の多さから、あまり使うことはないそうですが、効果はメサラジンより高いそうです。
坐薬・注腸剤
坐剤は直腸を中心に作用し、注腸剤は直腸からS状結腸、下行結腸あたりまで作用します。
潰瘍性大腸炎の中でも下行結腸より下部、特に直腸の炎症が強い場合、また直腸型のクローン病に用います。
(ペンタサ坐薬、ペンタサ注腸、サラゾピリン坐薬)
直腸より上部への作用は単独では期待できませんが、経口薬と併せることで作用範囲が拡がります。
用法は通常1日1回寝る前に使用します。
新しい注腸剤『レクタブル』
レクタブルは、フォーム剤という泡状の注腸剤で、有効成分が柔らかい泡状になり、腸内に広がります。そのため、漏れにくく、直腸~S状結腸あたりまでの患部に広く長くと留まり抗炎症効果を発揮します。
用法は通常1日2回。
漏れにくいため立ったまま投与できることも特徴ですね。
有効成分は、『ブデソニド』という抗炎症作用を有する『副腎皮質ステロイド剤』の一種です。
ブデソニドはステロイドではありますが、局所作用型で、局所で作用した後に肝臓ですぐに分解されるため、全身作用が少ないことから、内服薬に比べて安全性が高くなっているのも特徴ですね。
注腸剤の使い方↓
※この図解、笑ってしまうかもしれませんが、マジです。
※お薬情報の参考元:IBDプラス/潰瘍性大腸炎の治療で使用する主なお薬一覧
その他の内科治療
- ●免疫抑制剤
- ●ステロイド製剤
- ●生物学的製剤
- ●JAK阻害剤
※長くなるので次回から別途お話します。
クローン病と違い、5-ASAを大腸や直腸へ届ける工夫がなされた製剤がとても多いですね。
次回はクローン病でも使用される免疫抑制剤について、おさらいしつつ、潰瘍性大腸炎でのみ適応となっているお薬のお話をしていきます。
サクッと潰瘍性大腸炎の症状・治療の概要を知りたい方はコチラ↓

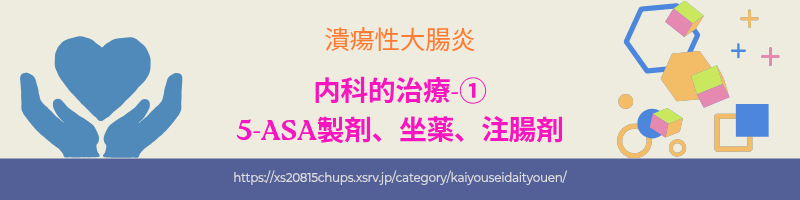

コメント