当サイト、Bloggerより引っ越してきましたので今となってはあまり関係ない話なのですが、この記事を作成したときちょうど私自身が大腸内視鏡検査でしたので、私の体験談も併せてお話しております。
それでは、IBDでは大腸内視鏡検査でどんなところをチェックするのか、ご説明します。
※大事なところばかりなのでアンダーラインが多くなっています。
大腸内視鏡検査で見るポイント
大腸内視鏡検査は、IBDに限らずどんな方も一生のうちに一度は受けることになるでしょう。
検査内容は読んで字の如く、肛門から内視鏡を挿入し、直腸から主に大腸、そして小腸の終わり(末端あたり)までをカメラで直に見て調べる、という検査です。
この検査では大腸ポリープや大腸憩室炎、大腸がんなもの発見にも繋がるため、重要な検査となります。
IBDでもなく、一般的な健常者で、とくに自覚症状がなくとも、50代60代のうちには一度は人間ドッグなどで行い、現状の確認と病があれば早期発見ができますので、なるべく受けましょう。
さて一般的なケースではなく、IBDの場合の検査のお話です。
IBDの場合、やはり潰瘍の発見とその種類や程度の強さ、狭窄など病態の現状把握になります。
IBD疑いの場合も同様に、これらの有無が『確定診断』の決定打になりますので必須の検査です。
ではIBD、とりわけ『クローン病の腸管にみられる潰瘍をはじめとした特徴はどんなもの?』ですが、
・『肉芽腫』と呼ばれる特殊な腸壁にみられる構造、
・潰瘍が丸いものではなく腸管に対して縦に細長く走る『縦走潰瘍』、
・ごつごつと石を敷き詰めたような潰瘍の『敷石状病変』、
・非連続性の病変という『病変と病変の間に正常部分が存在している』などの特徴、
・『狭窄』の有無です。
狭窄とは狭い所のことをいいますが、どうして狭くなるのかという原因は、潰瘍という深い傷ができる→修復する→この際にぎゅっと肉が引き締まる→潰瘍ができる→修復される→引き締まる、の繰り返しで極端に腸管が狭くなってしまう、それがクローン病に多くみられる狭窄です。
強い狭窄がありますと、内視鏡が通らないこともあります。このレベルですと厳しい食事制限をしないと食べたものがすぐに詰まり、『腸閉塞(イレウス)』を起こしてしまいます。
※狭窄についてはまた別途、詳細をご説明します。
これらの特徴が在るか否かで、クローン病であるかその他の病かが別れ、存在が確認できた場合、はじめて確定診断となり、特定疾患と認定され、国からの補助が受けられるようになります。
ですので、この確定診断が得られるまで、どれだけしんどくてもクローン病としての治療はできませんし、医療費も高額になります。
確定診断された後、高額医療費等で払い戻しがありますが、あとから返ってくるとはいえ先に支払わなければならないので家計は厳しいです。
『大腸内視鏡検査の準備-①制限食』に続きます。
カテゴリー『検査』はコチラ↓
サクッとクローン病治療の概要をまとめて知りたい方はコチラ↓

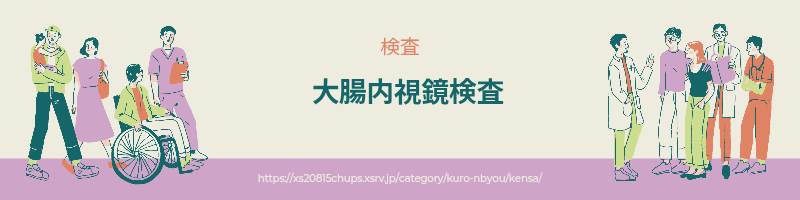
コメント