これまで薬物療法についてお話してきましたが、IBDの治療は残念ながら薬物だけでコントロールできるものではありません。薬物だけでコントロールできればQOLが高く快適で文化的なのですが、現代ではまだそれはとても難しいです。
それは、抗原(食事の成分や腸内細菌など)に免疫が過剰に反応し炎症が起きてしまうため、食事はダイレクトに影響があるからです。
そこで薬物療法と併用していく治療が、『栄養療法』になります。
今回から、『薬物療法』と併用していく『栄養療法』について順を追って解説していきます。
栄養療法とは?
栄養療法とはありていにいって、『食事制限と栄養剤による栄養の補給』です。
望ましい食事にもる効果『食事療法』と後述する経腸栄養剤での栄養摂取と併せ『栄養療法』とする、と捉えましょう。
※栄養の補給については経腸栄養剤にて後述します。
食事の制限についてまず先にお話しますが、このへんはサラッといきます。以前もお伝えしましたが昔と今とで医療サイドでも考え方が変わっていますし、先生によって方針も違いますし、なにより病態のステージと、腹痛や下痢を誘発する食品は体質による個体差がとても激しいので、『コレ!っていう確定のもの』はありません。
それを踏まえた上で、病院が推奨するほとんどの方に『共通の標準的な食事制限』についてお話します。
食事制限で勘違いしてはいけないこと
最初に強くお伝えしたいのは、食事制限とはいっても、
『各種栄養素の適正量摂取』は絶対です。
健常者のダイエットも含めてどんな人間も共通で、なにかを絶てばイイか、なにかを大きく制限すればイイか、なにかをたくさん摂ればイイか、というと決してそうではありません。
必要のない栄養素はありませんので、各種栄養素の適正量摂取は絶対なのです。
そしてその適正量を見極められるのは医師と栄養士になります。
専門家の方々と常に情報を共有し相談し合って自分に合う食事と栄養素の適正量を摂取しましょう。
しばしば、SNSなどで「◯◯で治す!」みたいな投稿を見かけますが、お腹にとって有意義な栄養素というものは確かに存在しますが、「治る!」というわけでは決してありません(現代医学の見地)。
そうした誤認識から過剰に摂取してしまうことで引き起こされる過剰症やアレルギーの発露などの危険がありますので、安易にネットの情報には飛び付かないよう心がけましよまう。
繰り返しますが、知りたいことがあったはまずは先生へ質問・相談です。
食事制限の基本指針
食事の基本は、『高カロリー』、『低脂肪』、『低残渣』の食事で適正量摂ることになります。
※高カロリーを摂取するのが難しい→後述の経腸栄養剤になります。
それではクローン病の食事について、今回は制限することが望ましいとされている基本的な食品を紹介します。
- ①脂質制限(低脂肪)
- ②たんぱく質制限
- ③難消化性食物繊維制限(低残渣)
- ④シュウ酸制限
- ⑤アルコール・カフェイン・刺激物制限
- ⑥乳製品
- ⑦アレルゲン制限
- ⑧禁煙
①脂質制限(低脂肪)
脂は消化にかかる負担が大きく、下痢も起こしやすいです。下痢を起こしやすいと炎症細胞が腸管に集まり病態を悪化させます。可能な限りダメージを減らし下痢を繰り返すことをまず避けるようにしなければなりません。
また『クローンの維持的療法時の脂肪摂取と累積再燃率』、というのがありまして、これによると、脂肪摂取量が再燃率に影響していると報告されています。
摂取量の目安は1日に30gとなっていますが、このあたりのことは後述します。
※矛盾するようですが、寛解期であればそれほど強い制限をしなくても大丈夫なこともあります。自覚症状と相談してある程度個人の判断に委ねられます。
※私は現在のステージではあまり制限していません。
②たんぱく質制限
クローン病は、動物性のたんぱく質が身体中に抗体をつくり、同様の食事を続けることによってたんぱく質を外敵と誤って認識してしまい過剰に反応してしまう、つまりアレルギーですね。たんぱく質はアレルゲンとなり炎症を起こすキッカケになっているのではないかと、近年判ってきました。
ですので、良質なたんぱく質として豆や鶏肉が挙げられ、対し脂も強い牛肉などは控えるよう指導されることが多いです。
肉を避けつつ、しっかりとたんぱく質を摂取することはなかなかに難しいです。
※やはりステージと、抗体を作ってしまう食品や種類には個体差はあります。
これを食べたらイッパツで下痢や腹痛、という症状の方は勿論制限する必要がありますが、なにも変化がないという寛解期の場合ですと制限は緩く、個人の判断に委ねられます。
※私は現在のステージではあまり制限していません
③難消化性食物繊維制限(低残渣)
難消化性食物繊維というのは、そもそも人間はこれを分解する消化酵素を持っていません。
健常者の場合ですと、この難消化性食物繊維は大腸で水分を吸ってくれて下痢予防になったり便がつるりとでやすくなったりとメリットが大きいですが、消化されないということは分解されない、小さくもならないということで、クローン病は少なからず狭窄があるので詰まりの原因となり、腸閉塞の原因になります。
またそもそも消化できないものというのはお腹にかかる負担も大きいものです。クローン病の場合は腸管へのダメージにもなりますので極端に制限します。
硬い、筋っぽい、ケバケバしてる、歯切れが悪い、そういう繊維はだいたいアウトと思ってください。
またイカ、タコ、エビなど消化に悪い魚介類も同様に消化に悪く詰まりやすいので制限します。
※個体差関係なく、これらは制限することになります。
※私は狭窄あるので厳しく制限してます。
④シュウ酸制限
クローン病は結石ができやすい傾向があります。シュウ酸を多く含むほうれん草やチョコレートなどを制限する場合があります。
原因は多々あり一言では言えませんが、下痢を繰り返すことで脱水気味になっていると結石はできやすいです。これは健常者でも同じですね。
※個体差もあり結石ができにくい方もいます。
また、ほうれん草やチョコレートばっかりやたら大量に食べる人なんてそうそういないので、それほど気にする制限ではないかと思いますし、医師もあまり強い制限はしません。制限する説明はしますが個人の判断に委ねられることが多いです。
なにかを厳しく制限するというより、水分をしっかりと摂取することのほうが肝要になるかと思います。
※私は出来やすいです……水分多くとってます。
⑤アルコール・カフェイン制限・刺激物禁
アルコールもカフェインもいずれも消化器にとっては刺激物になります。いたずらにダメージを与えては症状が悪化しますので制限します。
トウガラシ等の刺激物も腸管へのダメージしかありませんので基本的には禁止です。
※お酒飲んでもお腹全然下さない、コーヒーじゃぶじゃぶ飲んでもお腹痛くならないという方も少なくありません。
ですので厳しく禁止する先生もいますが個人の判断に委ねる先生もいます。
※私はお酒は何故か全然平気ですが、コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶、ほうじ茶、茶類すべて全滅です!めっちゃお腹痛くなります。
コーラでお腹ゴロゴロするのにビール飲んでもまったく不変な理由がサッパリわからない!コーラのカフェインなんて微々たるものなのに。
茶類はすぐお腹にきますね、カップ半分も飲めない。
リポDのようなエナジードリンクは一本ならなにも起きないです。8時間後に試しにもう一本飲んだらめっちゃ気持ち悪くなって吐きました。
これも大きな個人差ですね。
⑥乳製品
日本人は健常者でも乳糖不耐性といって、牛乳を分解するのが苦手な体質の方が多いです。お腹ゴロゴロきちゃうやつですね。
加熱処理すれば健常者でしたらなにも問題ありません。
最近では乳糖を分解してある牛乳も市販されてますよね。良い時代になりました。
ですが、IBDの場合ですと脂肪が多いので控えめにしたほうがよいです。
ローファットミルクやスキムミルクが推奨されています。
また、植物性クリーム(コーヒー等に入れるポーションミルク)はトランス脂肪酸が多く含まれているので避けたほうが望ましいです。
※こちらも、わりと平気な方も多いです。寛解期でしたら加熱してあれば量次第ですが大丈夫です。クリーム煮ですとか。
⑦アレルゲンを制限
たんぱく質制限と同様の理由で抗原となって腹痛や下痢を誘発し増悪させる食品ですね。
これはかなり判別が難しいです。たとえばパッチテストをすればわかるかというとそうでもありません。皮膚と腸管では少し違うようです。
免疫の病気ですからアレルギー症状が起きるとお腹も炎症を起こしやすくなりますが、お腹にとってのアレルゲンというものもあり、それらはダイレクトに腸管での炎症になります。
個体差が大変大きいですし多種多様なので主観で、代表的なものを挙げます。
・バラ科以外の果物 キウイ、パイナップル、ブドウ…etc
※私は加熱加工してあれば大丈夫です
・バラ科の果物
こちら結構アウトの方多いです。
サクランボ、アンズ、リンゴ、ナシ、イチゴ、ビワ、プラム、ウメ、ベリー系、アーモンド…etc
※私は全滅です!一口二口でお腹スンゴイ痛くなります。おまけに痛みが引くまで何時間もかかります
・ナッツ類
これは脂質も多いですね。
・先ほど挙げた肉類
⑧禁煙
タバコは腸管の毛細血管が収縮してしまい、それが原因で潰瘍になると考えられていますので原則禁止という判断をすることがあります。
※近年では血管の収縮と病態悪化との因果関係は以前より懐疑的になりつつあります。潰瘍性大腸炎では禁煙によって病態が酷く悪化するケースが多く、現在は潰瘍性大腸炎では禁煙はさせないことになってます。
クローン病も同様かというとまだそうしたエビデンスがありませんので医師は禁煙を促します。
このへんでしょうか。平気な人は平気ですしダメな人はほんとダメだったり、とにかく個人差が激しいです。
食事については以前触れましたがあんまり語りたくはないです・・・すみません。
次回は制限とは逆になるべく積極的にしたほうが望ましい食品についてお話していきます。

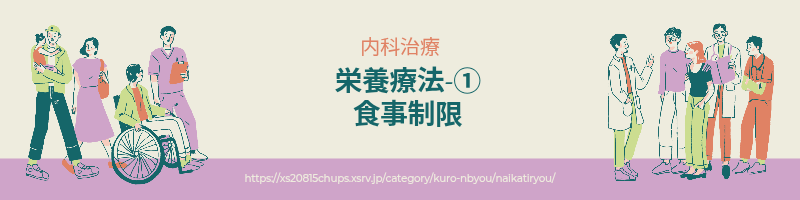
コメント