今回は前回に続き受給者証のおさらいと、更新時の注意点。とくに特例制度などについてお話していきたいと思います。
※軽症高額該当について知りたい方は、サッとスクロールして後半から閲覧ください。
まずは基本的なおさらい
特定疾患医療受給者証は年に一度の更新が必要
更新時期は都道府県によって違いがありますが、いずれも1年で更新が必要になります。
所得が変わったりすると自己負担限度が変わることがあります。
更新に必要な書類一式は自動的に郵送されてきますが、管轄によってはかなりギリギリに届くことがあります。
私の所では7月31日までに郵送しなければならないのですが、更新書類が6月末あたりに届くこともあります。
更新には、新規申請の際に主治医に書いてもらった『臨床調査個人票』が必要です。
自分で記入が必要な事項を書き、病院の書類窓口へ提出し主治医に書いてもらいますが、当然、他にも難病の患者さんはいらっしゃるので時期的に集中しますし、主治医がこれを記入し書類が完成するまでにはそれなりの時間を要します(病院によりけりなのでどれくらいという目安は難しいのですが、早くても2週間くらいかと)。
その為、ギリギリに更新書類が届くとかなり慌ただしくなります。
臨床調査個人票が完成したらすぐに受け取り、すぐに保健所へ郵送できるように他の書類は速やかに揃えておくと良いでしょう。
必要な書類
『更新手続きのご案内』が書類一式に同封されてますのでしっかり確認しましょう。
①特定医療費支給認定更新申請書
更新書類一式と一緒に郵送されてきます。記入の難しい点はなく、自分ですべて書くことができます。
②臨床調査個人票
主治医に記入してもらう書類です。必要事項記入し、速やかに病院へ提出しましょう。
・臨時調査個人票の審査
認定されるためには、『診断基準(対象の疾病に罹患しているか)』と、『重症度基準(症状が一定程度あるか)』
この2つを満たす必要があります。
認定基準は疾病ごとに厚生労働省や難病情報センター等のHPで公開されています。
※重症度基準には、「どの検査が絶対的に必須」のように決まったものはないようです。クローン病の場合は『IBDスコア』が判断材料になりますので、この項目に関して調べるための検査を実施し、主治医が結論を出し、臨床調査個人票に記載しますので、自分で「あの検査をやらなきゃ!」と意識する必要は基本的にないかと思います。
IBDスコア↓
※潰瘍性大腸炎の場合は詳しくはわかりませんが、クローン病と同様に重症度を測るための項目のリストがあります。
③健康保険証のコピー(患者と支給認定基準世帯員全員分)
『支給認定基準世帯員』とは、次号負担限度額の算定の基準となる方で、患者及び感じると同一の保険に加入している方を指し、患者の加入する公的医療保険の種類によって異なります。
※住民票上の世帯員ではありません。
これはどういうことかと言いますと、家族のうち、社会人が数人いて、勤めてる会社がそれぞれ違って、それぞれ異なる健康保険に加入していた場合、『患者が加入している保険と同一でない家族は関係がない』、ということです。その為、世帯員とはいっても住民票上の世帯員とは別なのですね。用語で紛らわしいですよね。
独力で生活されてる方は自分の保険証のみですが、家族の扶養に入っている場合、その同一の保険に加入している世帯員全員分の保険証のコピーが必要になります。
※例:夫(妻)の扶養に入っている場合は夫(妻)の保険証のコピーが必要になるということですね
④住民票の写し(世帯員全員分)
患者が18歳未満の場合は全員の続柄が記載された住民票が必要になります。
※マイナンバーの記載によって省略することができます。
その場合、マイナンバー確認書類(本人分と、本人確認書類のコピー)が必要になります。
これは、マイナンバーがわかる書類と、本人確認のための書類として免許証ですとか、マイナンバーと本人確認書類によって患者本人を正しく特定するためのものですね。一致するもの、です。
保健所に郵送する場合には『マイナンバーカード』のコピー(両面)だけで可能です。
今となってはマイナンバーカードをみなさんお持ちと思いますので、マイナンバーカードのコピーでOKです。
以上の書類はわかりやすいので間違えることはないと思います。
ややこしくなるのが以下の書類になります。
⑤本年度の市町村民税の課税状況のわかる確認書類(世帯員全員分)
これが大変わかりにくく、「んんー??」となりがちです。
どなたの分の確認書類が必要かは、『更新手続きのご案内』にフローチャートがありますので、「はい」「いいえ」を選択して必要な書類の確認をしましょう。
フローチャートではまず、『自分が加入している公的医療保険がなにであるか』、確認します。国民健康保険ですとか社会保険ですとか、それ以外の国民健康保険や、後期高齢者医療制度など。
次に進みます。『患者本人が被保険者か否か』。
こういう日本語苦手という方もいるかと思いますので説明しますが、被保険者とは、保険に加入している方本人のことです。たとえば父親がお仕事で家計をメインで支えている場合、お父さんが被保険者で、お母さん、子供たちは被保険者ではありません。扶養されている方は被保険者ではない、ということです。
次に、『被保険者は市町村民税が課税されているか否か』
普通に働いていれば課税していますね。お給料から引かれてるやつです。アルバイトやパートタイムで独力で生活されてる方でも、社会保険には加入されてると思いますし、市町村民税はお給料から引かれてると思いますが、しっかりと確認しましょう。
これで自分が揃えなくてはならない課税状況のわかる書類はフローチャートによって導き出されます。
該当する書類を特定できます。
たいていの場合、『特別徴収税額決定通知書源泉徴収票』のコピーですね。毎年5月末に会社に送られ、従業員へ渡されます。
非課税だった場合は、市役所でもらえる非課税証明書になります。
⑥特定医療費受給者証の自己負担限度額管理票のコピー
受給者証の、治療にかかった医療費を病院が記載する欄ですね。
更新を行う月以前の12ヶ月分すべてが必要になります。
はい、ここまでが、更新される方みなさん全員が必要になる書類です。
噛み砕いたので回りくどい説明になりましたが、『更新手続きのご案内』を見てもよくわからなかった際の参考になれば幸いです。
毎年のことなので、チェックリストを作成し、必要なものは明確にわかるようにしておくと翌年以降が楽になります。
また、郵送する場合、郵送料がいくらで何円分の切手が必要になるかも記録を残しておくとスムーズです。
定形外郵便で210円ほどかと思います。
さて、これで終わりではありません。ここからがちょっと難しい、該当する方のみ必要になる書類になります。
◯◯に該当する方って、どんなヒトが対象?
⑦軽症高額該当・高額難病治療継続の要件を満たす場合
※後述で詳しく説明します。
⑧生活保護等を受給している場合
⑨同じ健康保険に加入の世帯員の中に他に特定医療費(指定難病)あるいは小児慢性特定医療費の受給者がいる場合
⑩非課税の方で障害年金や遺族年金、その他の給付を受けている場合
になります。
⑦以外はありていに言いますと、特別生活が困窮していると認定されていたり、複数の指定難病を抱えていたり、なにかしらの給付を受けている方ですね。
それぞれの受給者証のコピーや、給付金にかかる証明書類が必要になります。
私が該当していないので、細かく説明することができないのですが、これらに必要な書類も、更新のご案内に記載されていますのでしっかりと確認をして揃えましょう。
⑦については『特例制度』になります。
特例制度とは?
・重症度基準を満たない軽症な方で受給者証の対象から外れていても、特定の条件を満たしている場合は受給者証の更新が可能という制度『軽症高額該当基準』と、
・治療にとても高い医療費がかかる高額難病で継続治療を受けている方の場合、自己負担限度額が下がるという制度『高額難病治療継続特例』があります。
●高額難病治療継続特例
こちらは、申請しますと限度額が下がるという家計にとって良いことで、更新のご案内を確認の上、該当される方は必ず申請しましょう。でないと家計大ダメージなので要注意です。
更新申請を行う月以前の12ヶ月のうち、6ヶ月以上特定医療費の総額が50000円を超える方が該当します。
自己負担限度額管理票を見て、1ヶ月の合計が50000円を超えている。それが6回(6ヶ月)あれば申請可能です。
気をつけなければいけないのが、必要な書類として上記の⑥のコピーだけではダメ、というところです。
①の申請書の『特例制度の認定申請』の欄に必ずチェック(レ点)を入れることを忘れないように注意。
●軽症高額該当基準
これが私たちにとって最大の悩みの種になるかもしれません。
細かく説明しますと、まず、重症度基準を満たさない軽症な方は、受給者証の更新ができない、(審査をクリアできない)場合があります。→『失効』
対象から外れる為、自己負担額は健常者の方と同じ3割負担であり、IBDのような特殊な先進治療をした場合は満額負担になります。
大変なダメージです。
・生物学的製剤もJAK阻害剤も必要ないどころか、標準治療薬である5-ASAさえも必要ない、通院の必要性すらないと判断されたとっっっても病態の安定している方は、指定難病の医療費がかからないので受給者証の必要がない、というわけで更新はされずに失効となります。
・これを良いことと捉えるか悪いことと捉えるかは個人によってまちまちです。
というのも、みなさん誰もが、「通院やだ」「薬もう止めたい」「こんなに薬飲み続け将来大丈夫なんだろうか」。様々な不安を抱えていることかと思います。
その為、失効となると喜ぶ方もまた少なくありません。確かに、治療の必要性がないというのは良いことに決まっていますよね。
しかし、私たちの難病に根治はありません。それまでずっと良好だったのに、ある時から突然に再燃する、という可能性もまた高いのです。
そうなった場合、受給者証がない状態ですと、高額な治療を受けることが大変厳しくなります。負担額が桁違いになります。
あらためて新規申請をする必要があり、審査が通り受給者証が届くまで治療が後手に後手に回り、最悪手術となってしまう可能性さえあります。
ここが人によって価値観がちがうのでむずかしいところですね。
素直に喜ぶか、マズイ!って思うか。
そんなとき、福音であるのが『軽症高額該当基準』なわけです。
軽症高額該当基準
国が定めた認定基準のうち、診断基準は満たしているが、重症度基準を満たさない場合に、
更新申請を行い月以前の12ヶ月のうち、3ヶ月以上特定医療費の総額が33330円を超える方が該当します。
自己負担限度額管理票を見て、1ヶ月の合計が33330円を超えている。それが3回(3ヶ月)あれば申請可能です。
たとえば、通院は4ヶ月に1回、血液検査くらいしかしないけど病態の確認は継続的にしている。その上で内服薬は標準治療薬を続けている。これだけですと条件を満たすには届きません。
これに加えて病態の寛解維持のために栄養療法を継続している(エレンタールやラコールなどを普段から飲んでいる)
となりますと、4ヶ月に1回、4ヶ月分の経腸栄養剤が処方されます。
4ヶ月ともなると相当な量です。この月は33330円を超えることになるでしょう。
12ヶ月でみたときに3回は超えている月があるはずです。
こうした場合に申請ができます。
この制度を活用しますと、受給者証を失効してしまう、受給者証がない年というものを生むことがなく、安心して過ごせます。
※ただし、継続的な通院、加療は必要になります。
受給者証とも通院とも全部オサラバしたい方は失効でも本懐かと思いますが、やはり先々に不安が残るという方は、この軽症高額該当基準を満たし受給者証を更新することをオススメします。
受給者証更新時の注意点などについては以上になります。
ちょっと説明が散文的になってしまいました。こういう事務的なことは不得手なものでわかりにくくてすみません。
少しでも参考になれば幸いです。
あくまでも、素人説明ですので、真に正しいことは難病情報センターへお問い合わせください。
難病情報センターはコチラ↓
カテゴリ『診断』一覧はコチラ↓

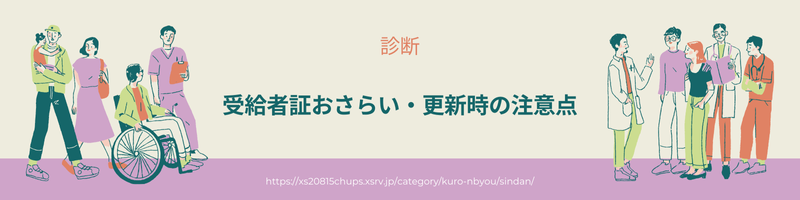


コメント